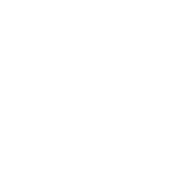How To repair
市販リペアキットでフロアーをDIY
ホームセンター等で売っているリペアキットの
パパリペアを使ってフロアーの補修を解説。
パパリペアを使ってフロアーの補修を解説。
1
高森コーキさんが販売している
リペアキットのパパリペアで補修してみる。
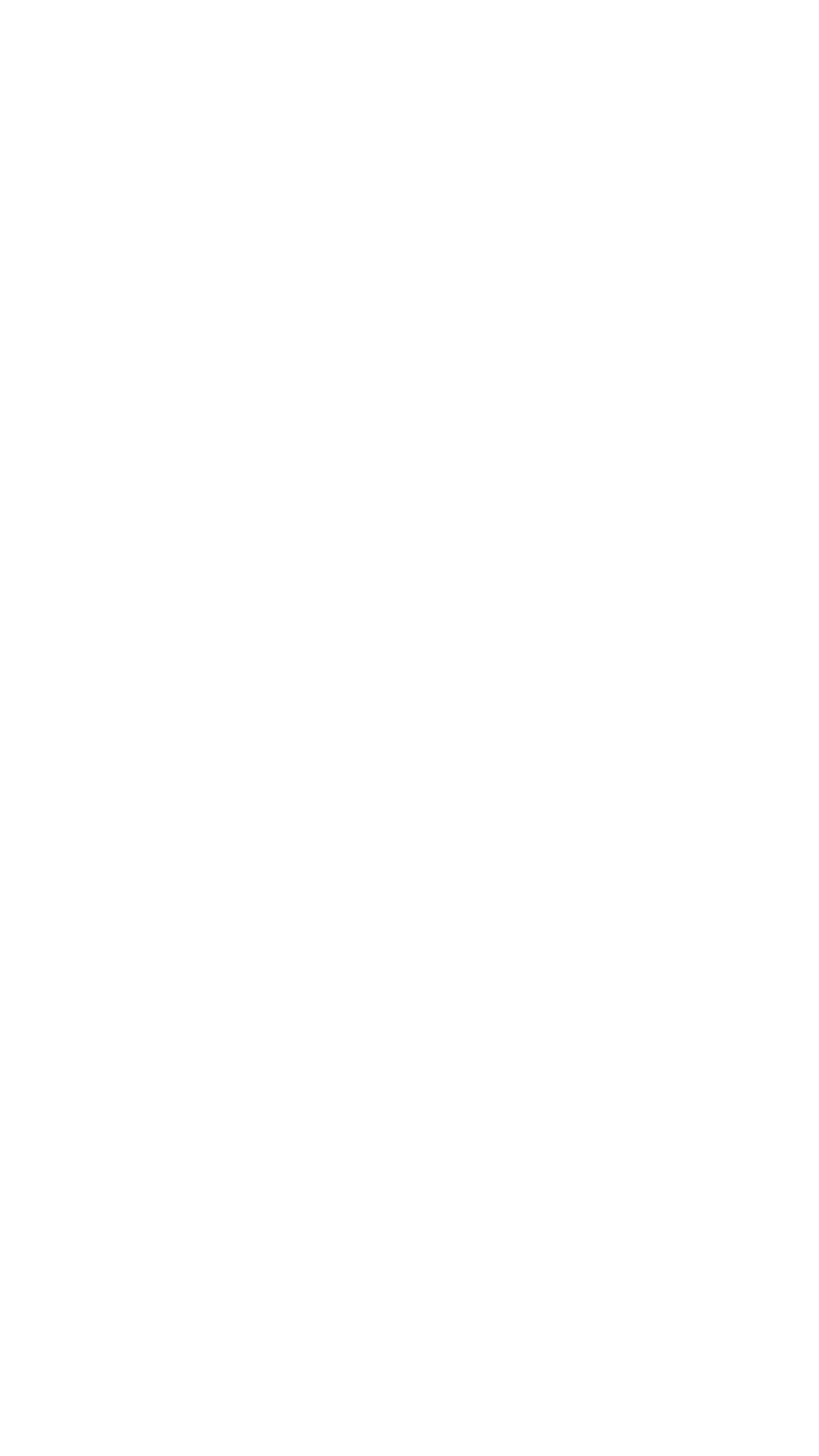
今日はパパリペアを使ってチョークドオークという柄のフローリングの補修をしてみます。DIYでフローリングの補修をしてみたい!そんな方のために参考になれば幸いです。リペアキット以外で用意して使用するものは、カッターと瞬間接着剤、硬化促進スプレー(なくてもOK)、ゴム手袋、少量の水,
です。
です。
2
フローリングの傷の下処理
今回は鋭利なものが刺さった傷で、フローリングの種類は、合板にMD F基材に特殊化粧シート仕上げのものです。最近のフローリングはこういうタイプが主流というか結構多いです。
一昔前は、合板に単板貼りが多かったですね。MD F基材はフローリングだけではなくドア枠材、窓枠、巾木、建具などに多く使われています。このMD Fは木質繊維などを加工したものなので、紙っぽい感じなので、補修するときは下処理が必要になってきます。
一昔前は、合板に単板貼りが多かったですね。MD F基材はフローリングだけではなくドア枠材、窓枠、巾木、建具などに多く使われています。このMD Fは木質繊維などを加工したものなので、紙っぽい感じなので、補修するときは下処理が必要になってきます。
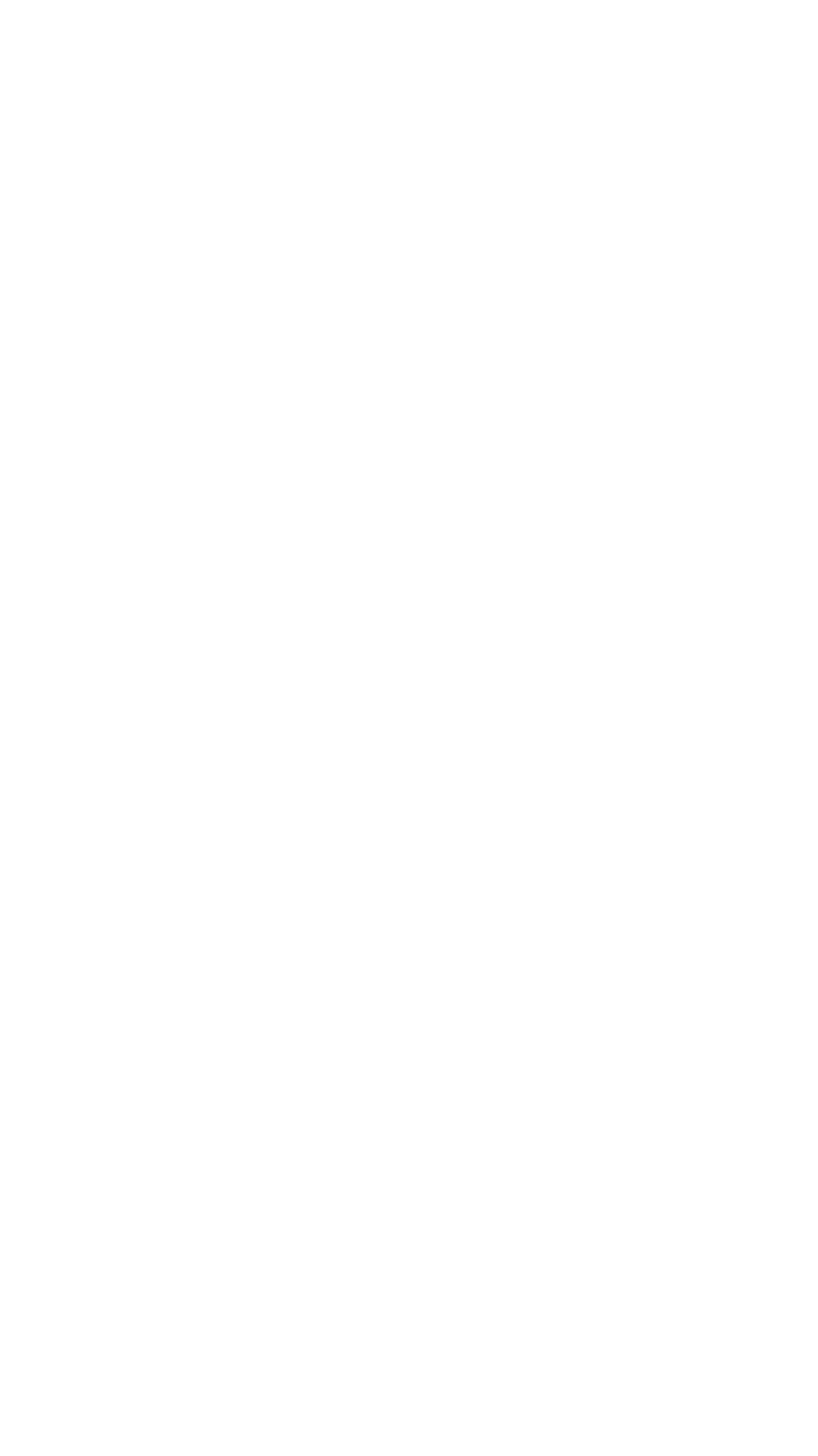
表面の化粧シートとMDFがぐずぐずな状態。
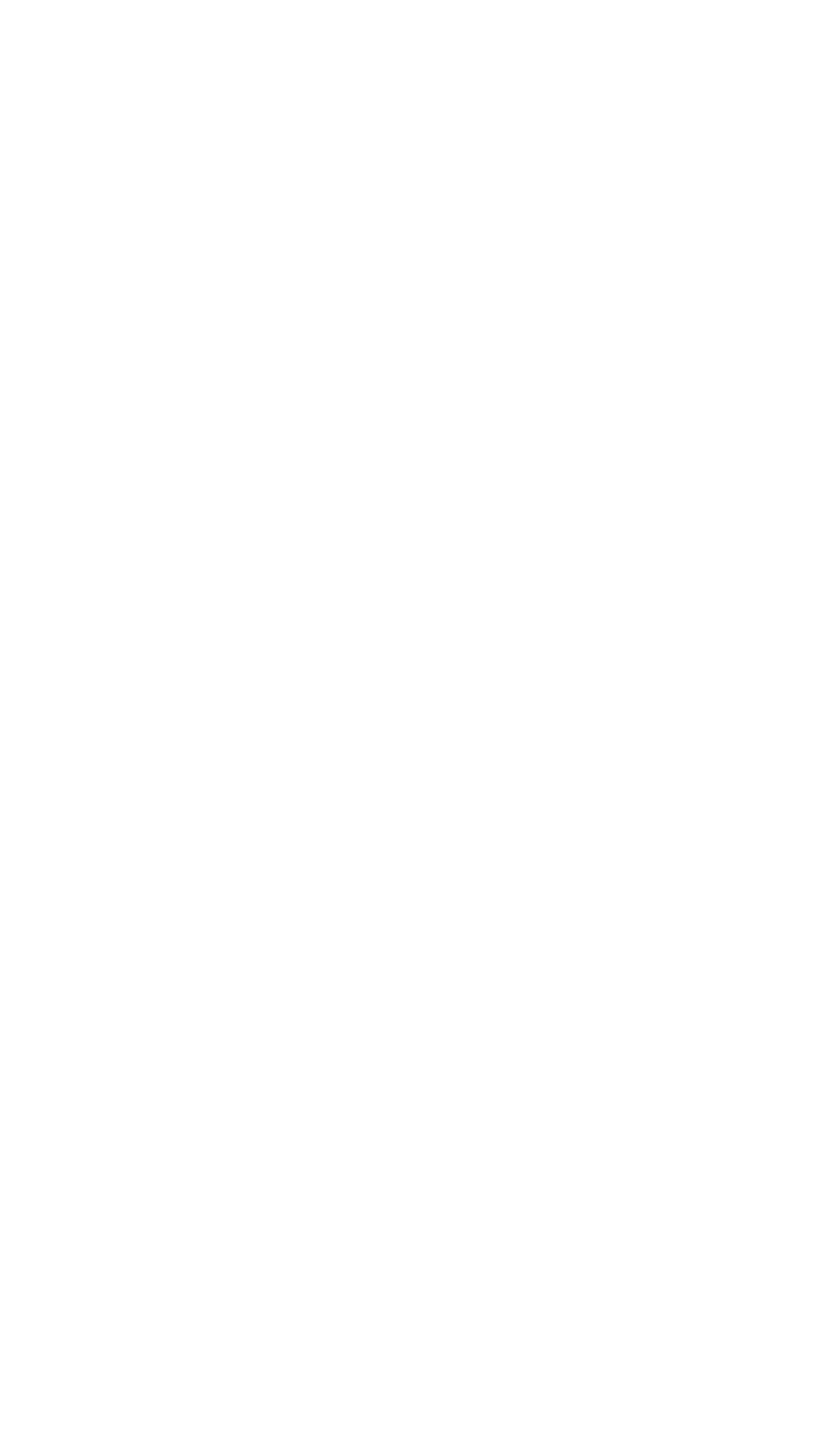
カッターで浮いているものを切り取ります。
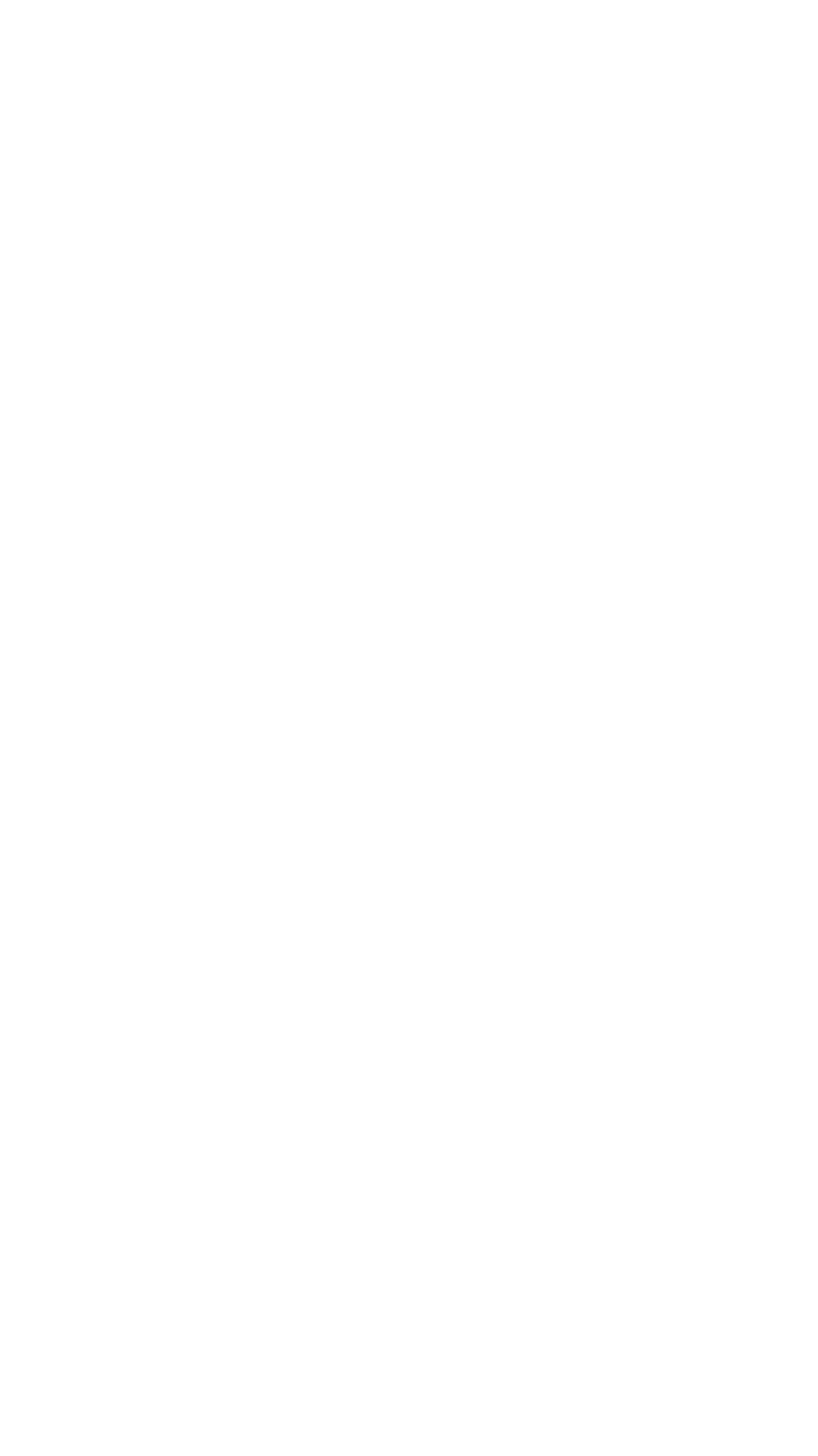
浮いているシートやMDFを除去します。
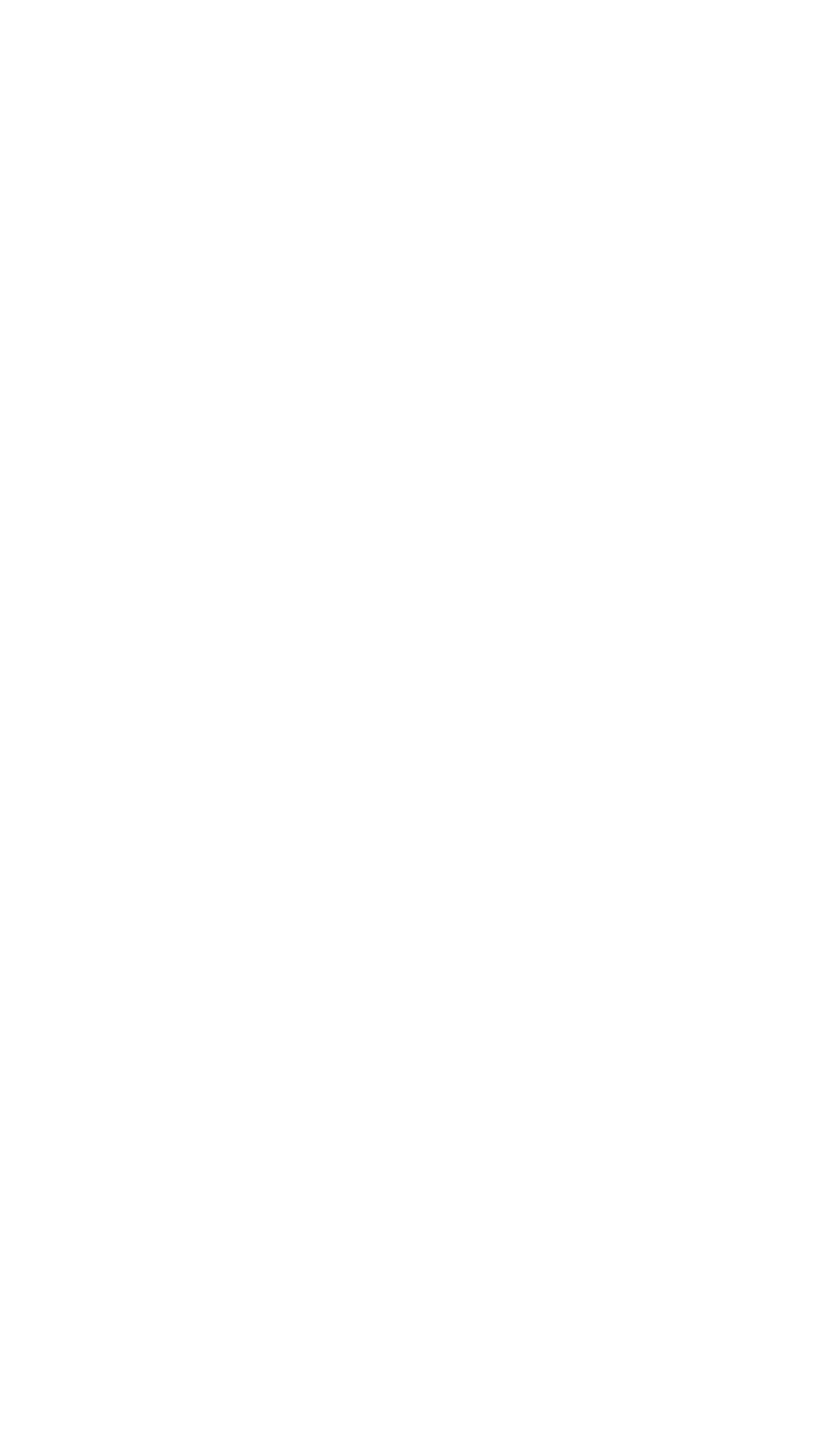
付属のサンドペーパー240番でMDFとシート周辺を研磨してならします。
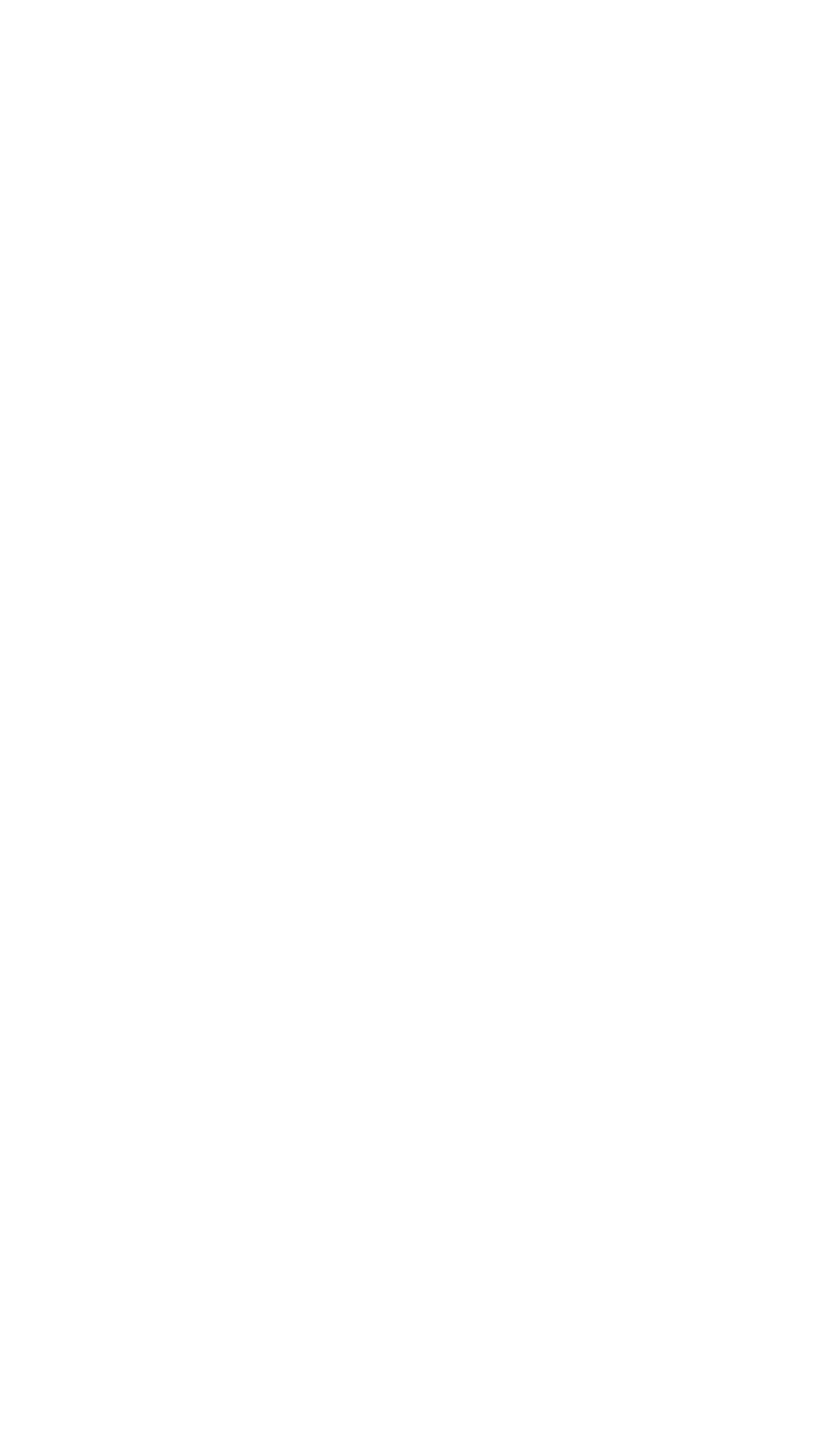
カッターのお尻で表面のシートを押すようにしてならしていきます。
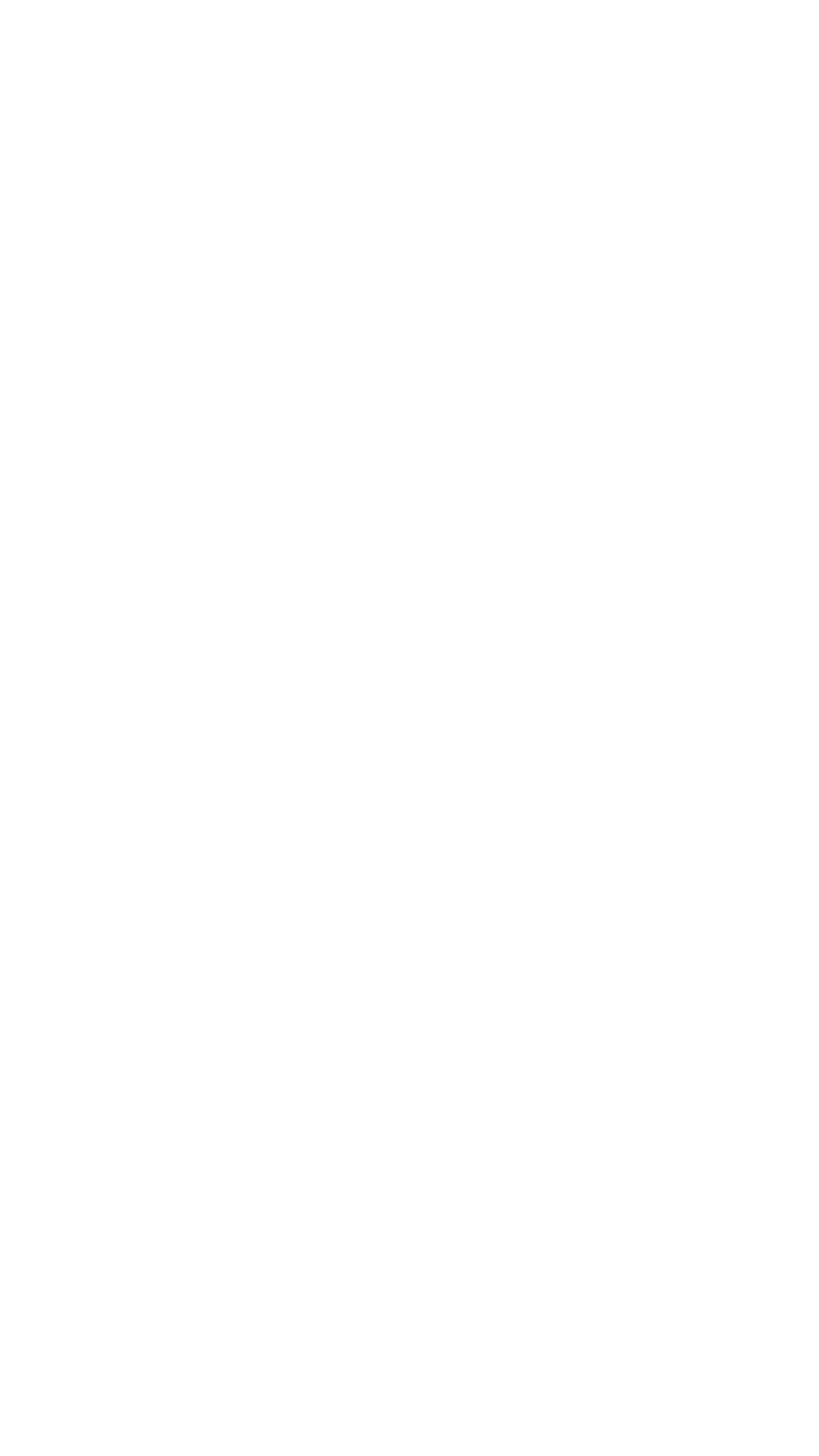
ジェル状の瞬間接着剤で表面につかないようにMDF基材に塗り込みます。通常は液状の瞬間接着剤を使うのですが、切らしていたのでジェル状を使っています。
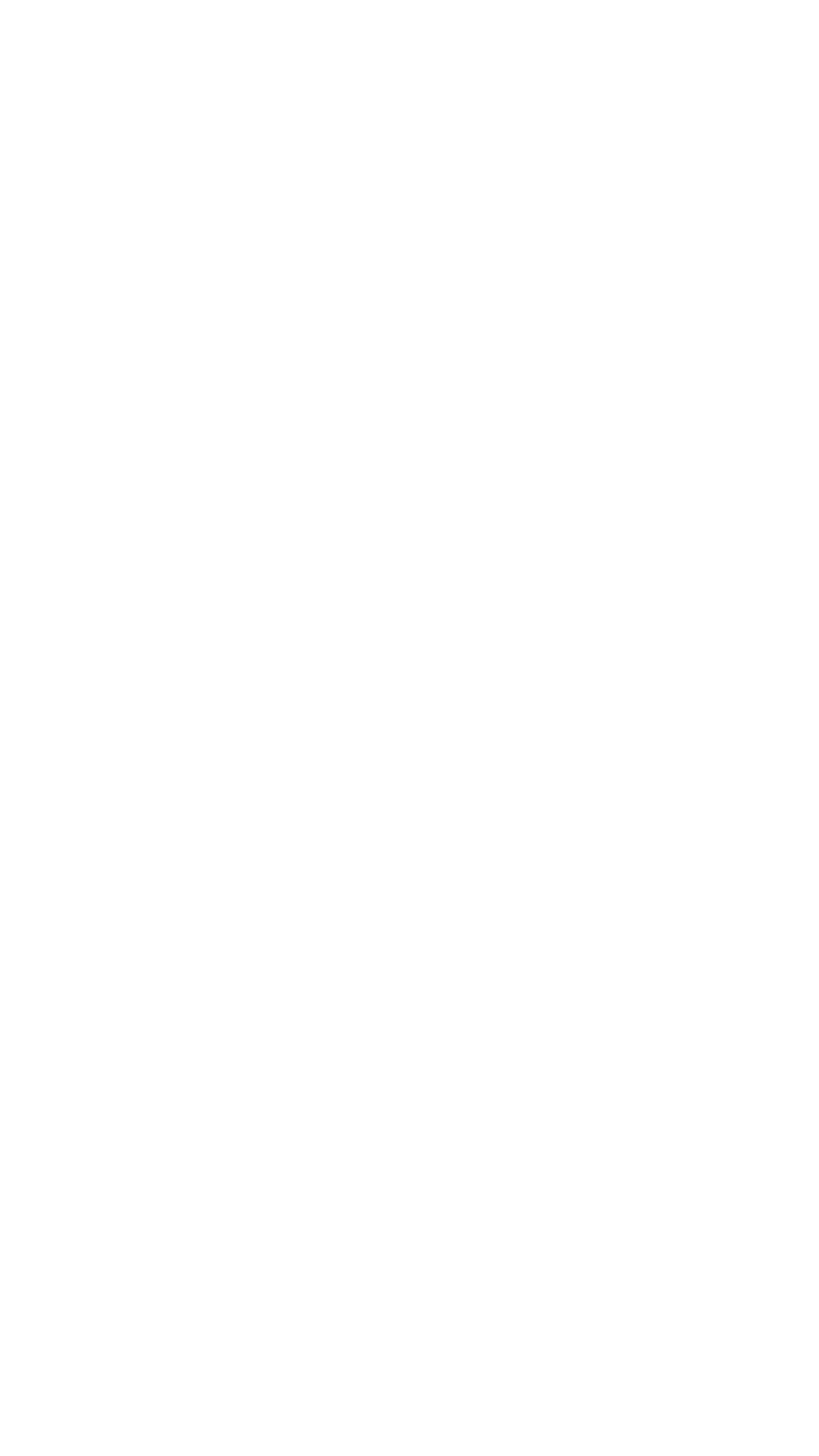
硬化促進スプレーを吹きかけて接着剤を硬化させます。ない場合は固まるまで待ちましょう。
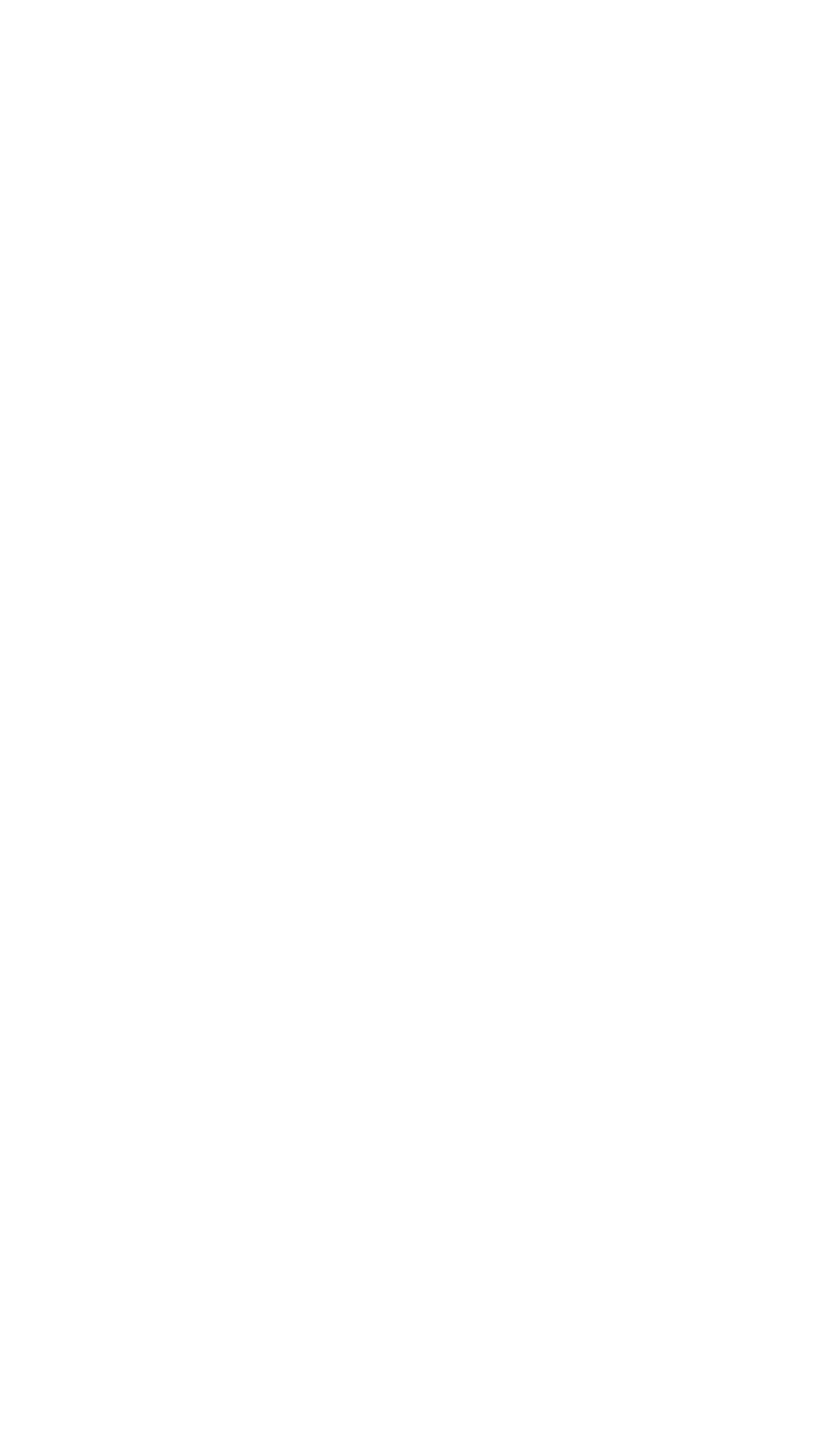
硬化したら、傷にもう一度240番のサンドペーパーで軽く研磨して足つけをします。この時に傷のない表面より出ているものがあれば切り取るか研磨で取り除きます。
傷で、できたシートと浮いているMDFを切り取り、サンドペーパーで軽くならしてから、カッターのお尻などでシートを押さえ込み瞬間接着剤でMDFとシートを固めてからまた軽く研磨。これで下処理は完了です。次は、傷にパテを埋めていきます。
3
パテ埋め作業
エポキシパテを練り上げて埋め込んでいきます。エポキシパテは主剤と硬化剤の2種類で構成されていて混ぜなければ硬化はしません。カラーパウダーを混ぜ合わすことで、色のついたパテが作れます。カラーパウダーを混ぜなくても薄茶色しているので、白のカラーパウダーを混ぜても真っ白のパテは作れませんのでご注意ください。
初めてリペアする方は、パパリペアの説明書の通り、傷周辺にマスキングテープを貼ってパテ埋めしてください。パテの硬化後もマスキングは剥がさずにそのままで、研磨作業します。詳しくは、後ほどの研磨作業で説明します。
初めてリペアする方は、パパリペアの説明書の通り、傷周辺にマスキングテープを貼ってパテ埋めしてください。パテの硬化後もマスキングは剥がさずにそのままで、研磨作業します。詳しくは、後ほどの研磨作業で説明します。
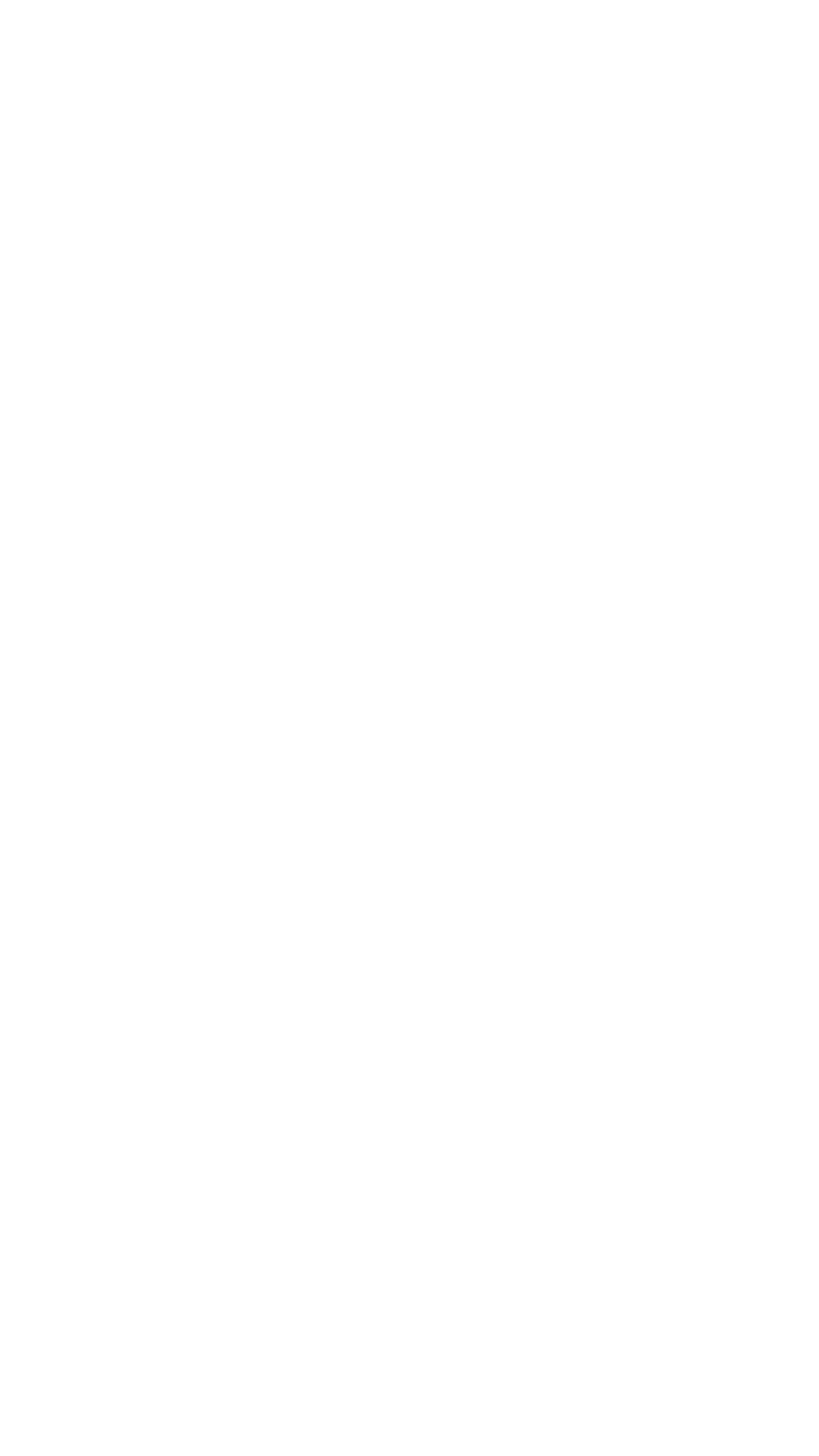
パテにはビニールが2枚で包まれているので外側のビニールを取ります。
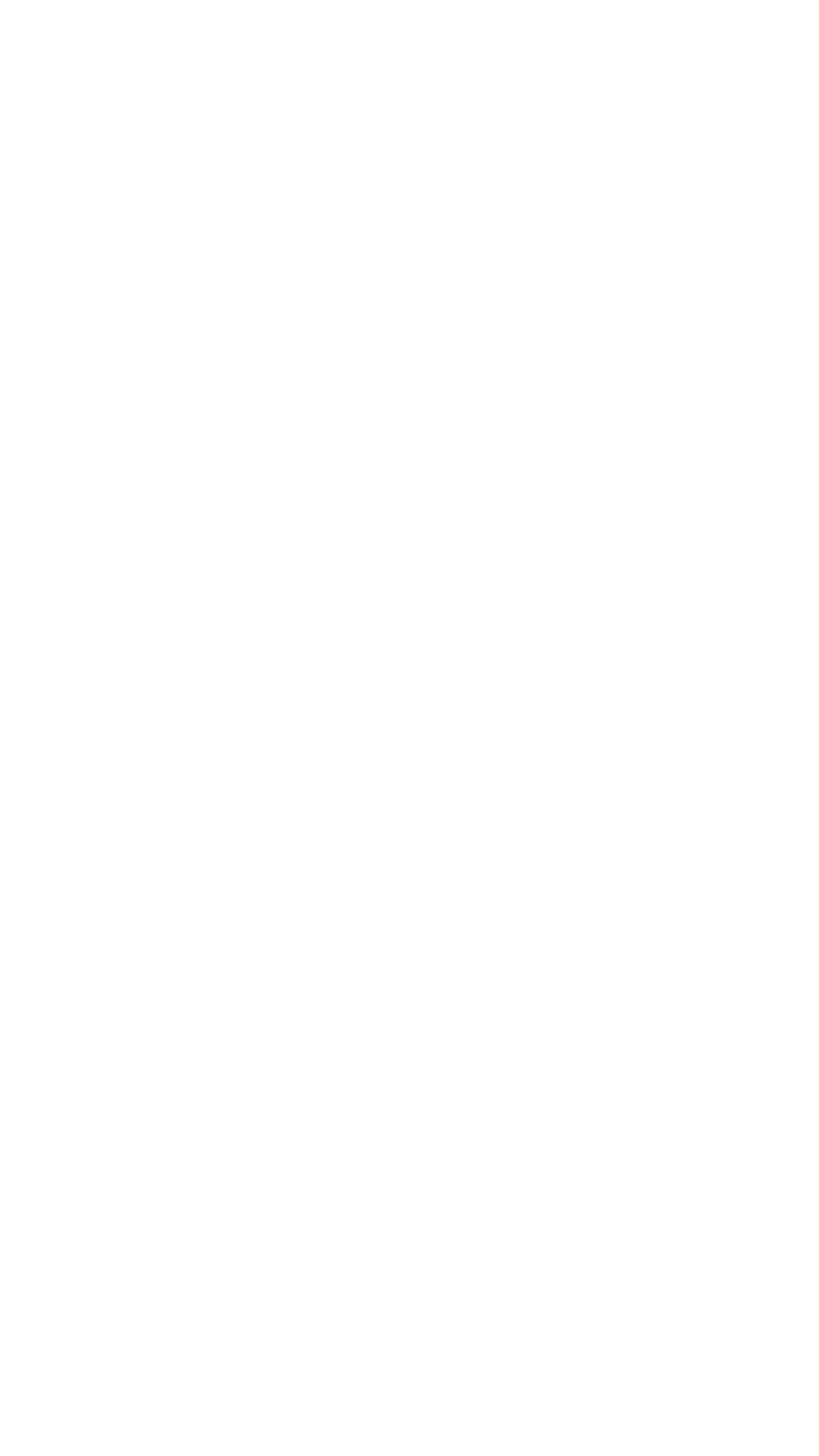
付属のビニール手袋を着用してパテを寝る準備をします。パテの小口についているシールを剥がします。
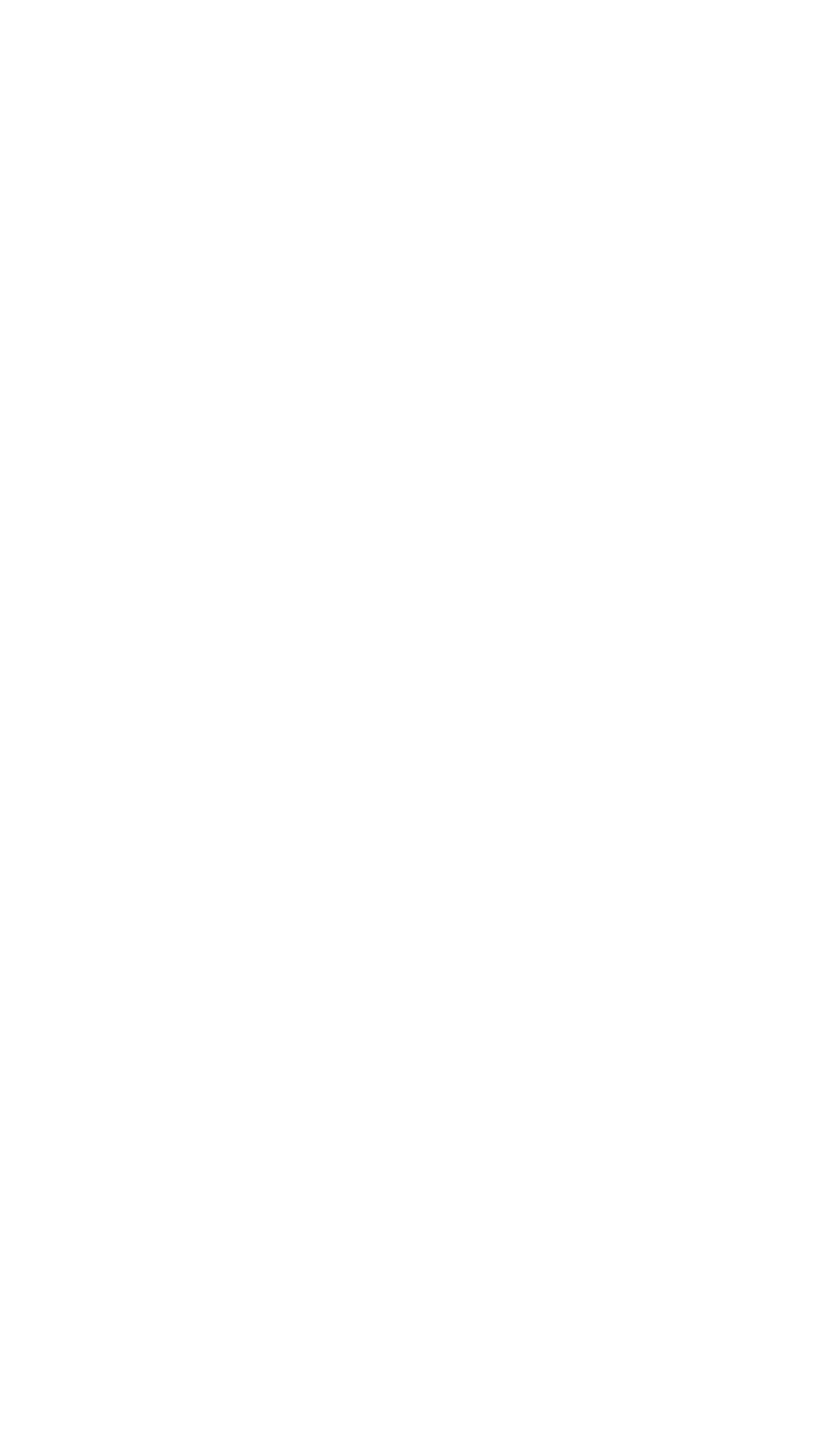
カッターで使う分量を切り取ります。パテに密着して巻いてあるビニールを剥いて切り取るか、ビニールを剥かずにそのまま切り取ってもどちらでもいいです。私のように空中で切り取らないで傷ついてもいい板の上で切り取ると切りやすいです。
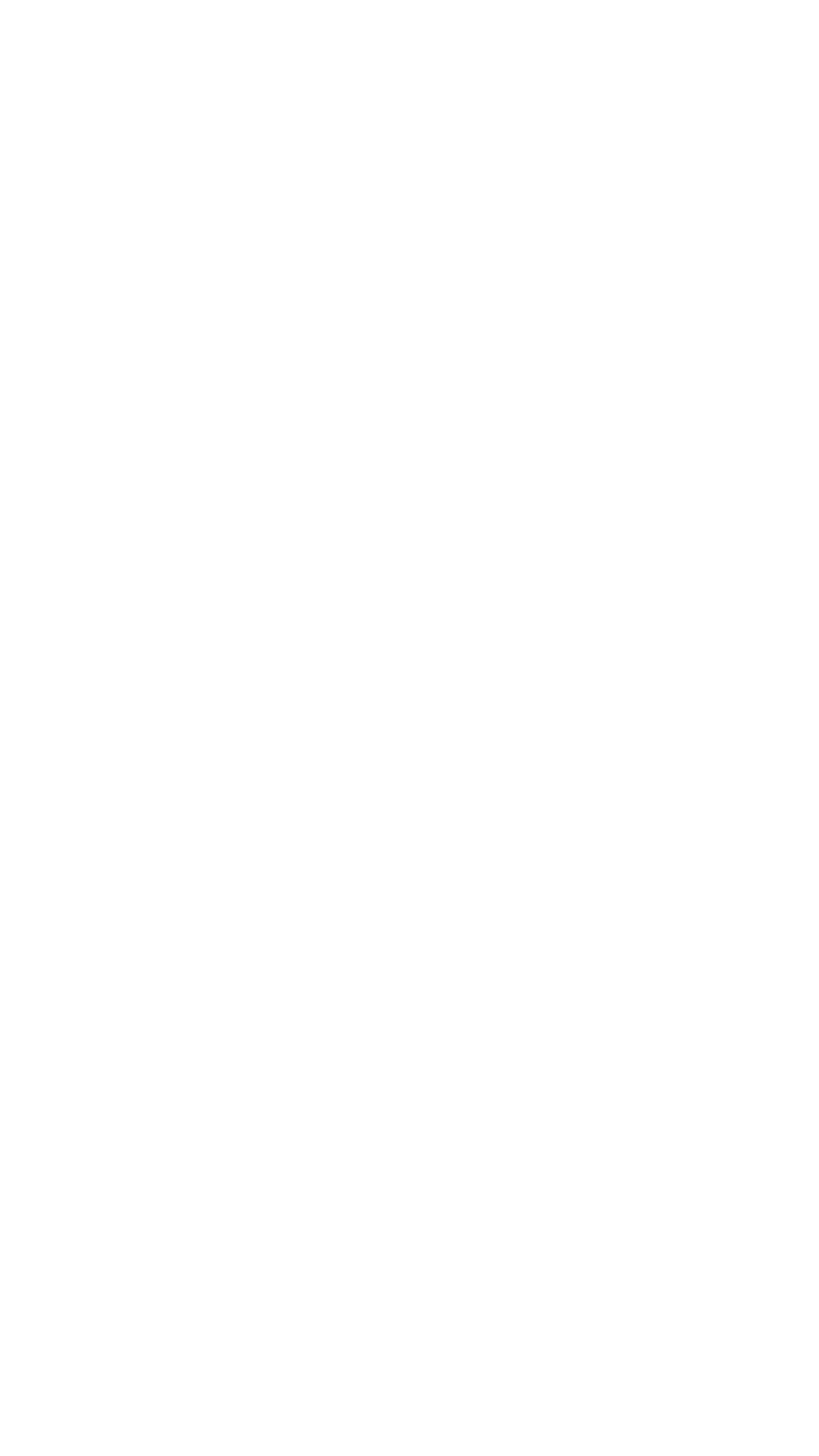
小口の乾燥を防ぐために、剥がしたシールを戻します。シールが破れた場合はラップなど巻いておきましょう。次に使うときに乾燥でカピカピになってしまうからです。
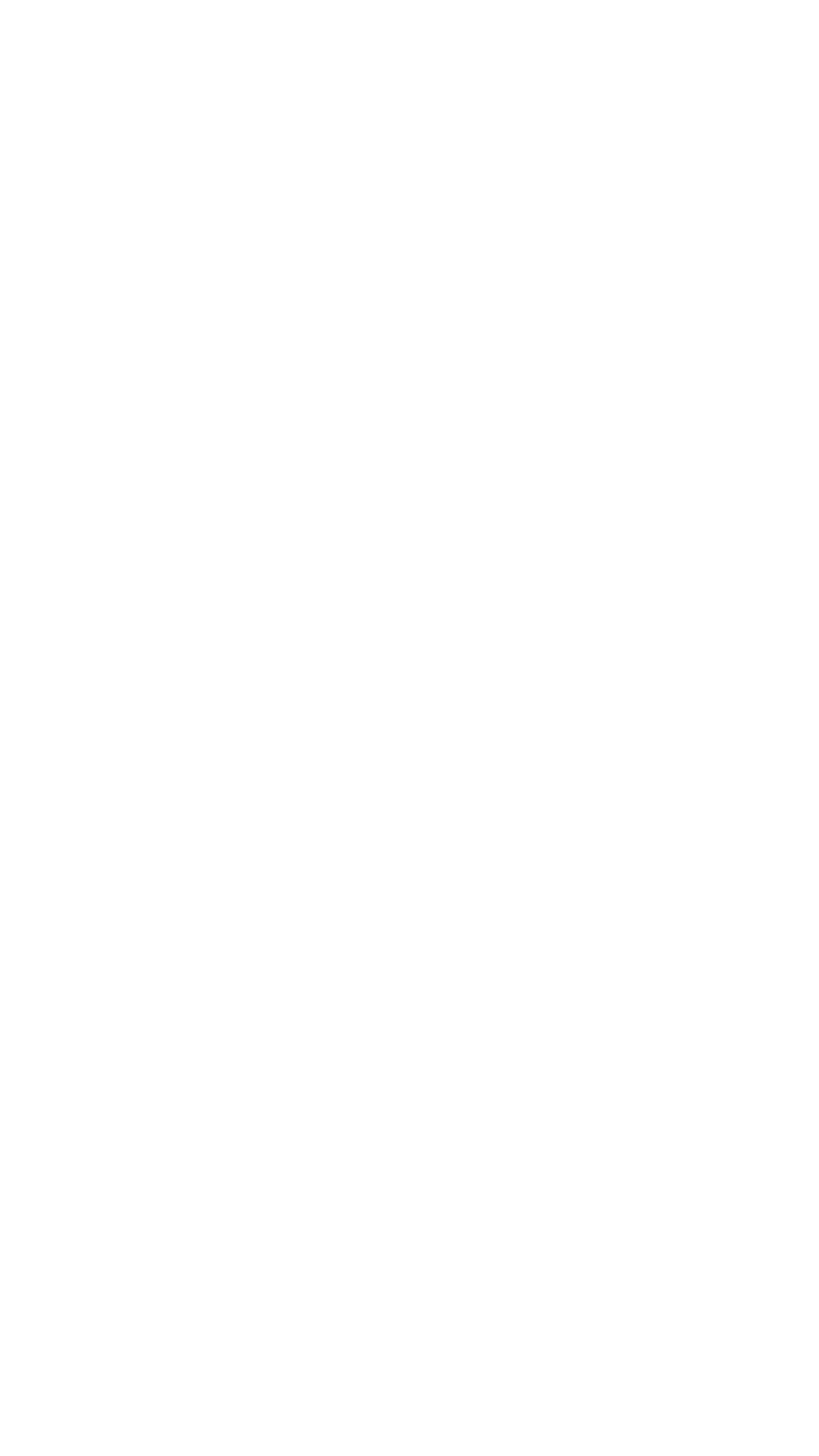
補修するフロアーに合いそうなカラーパウダーを選びます。
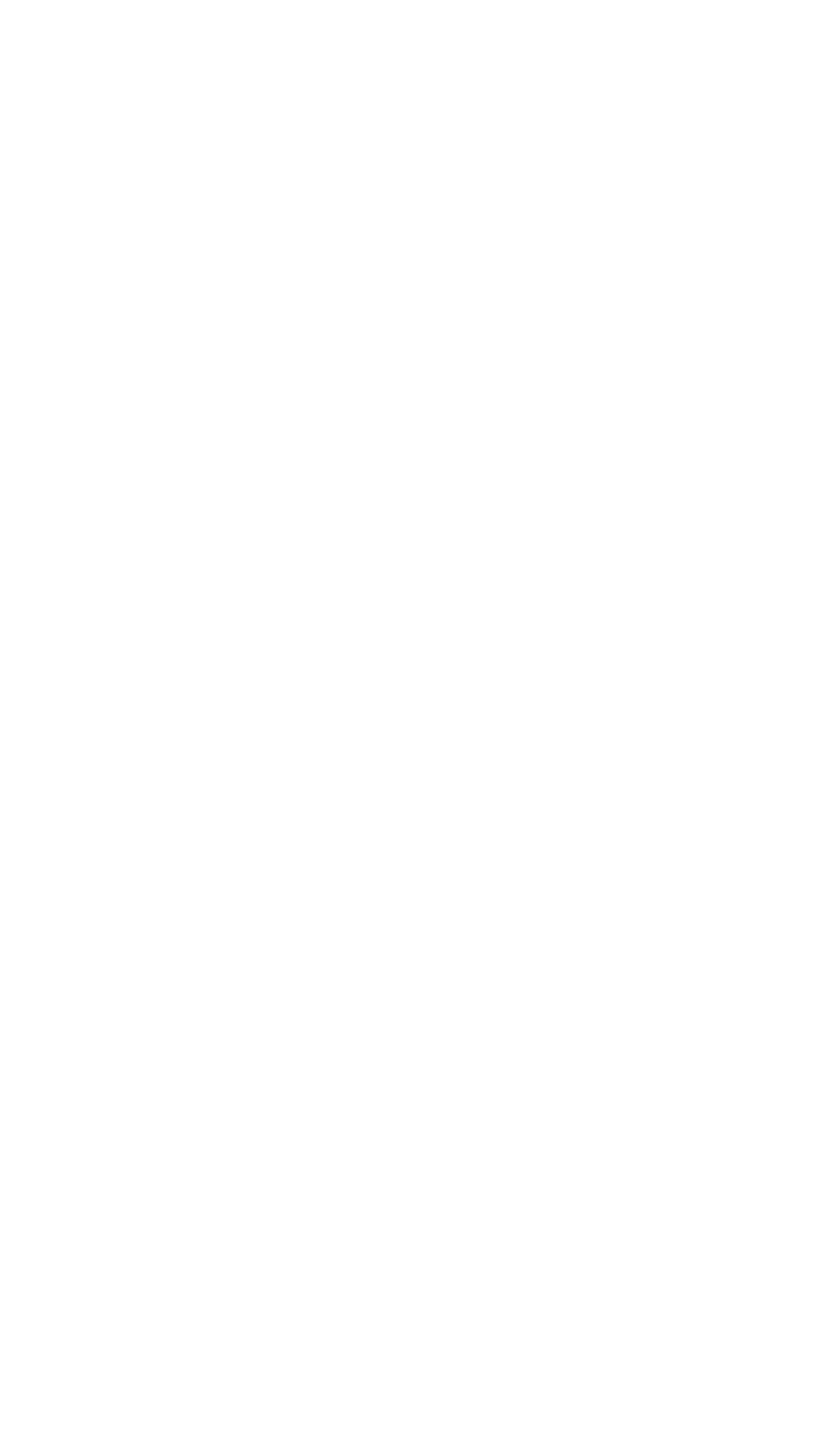
カラーパウダーの容器の蓋を開けるときは、紙の上などで行なってください。容器が小さいので画像のようにこぼしたりしちゃいます。パテに混ぜる時も同様で紙の上にパウダーを出して使うようにしてください。こぼした場合は拭き取らずに掃除機で吸ってください。拭き取るとフロアーの木目に入り取れなくなる場合がありますので。ご注意を。
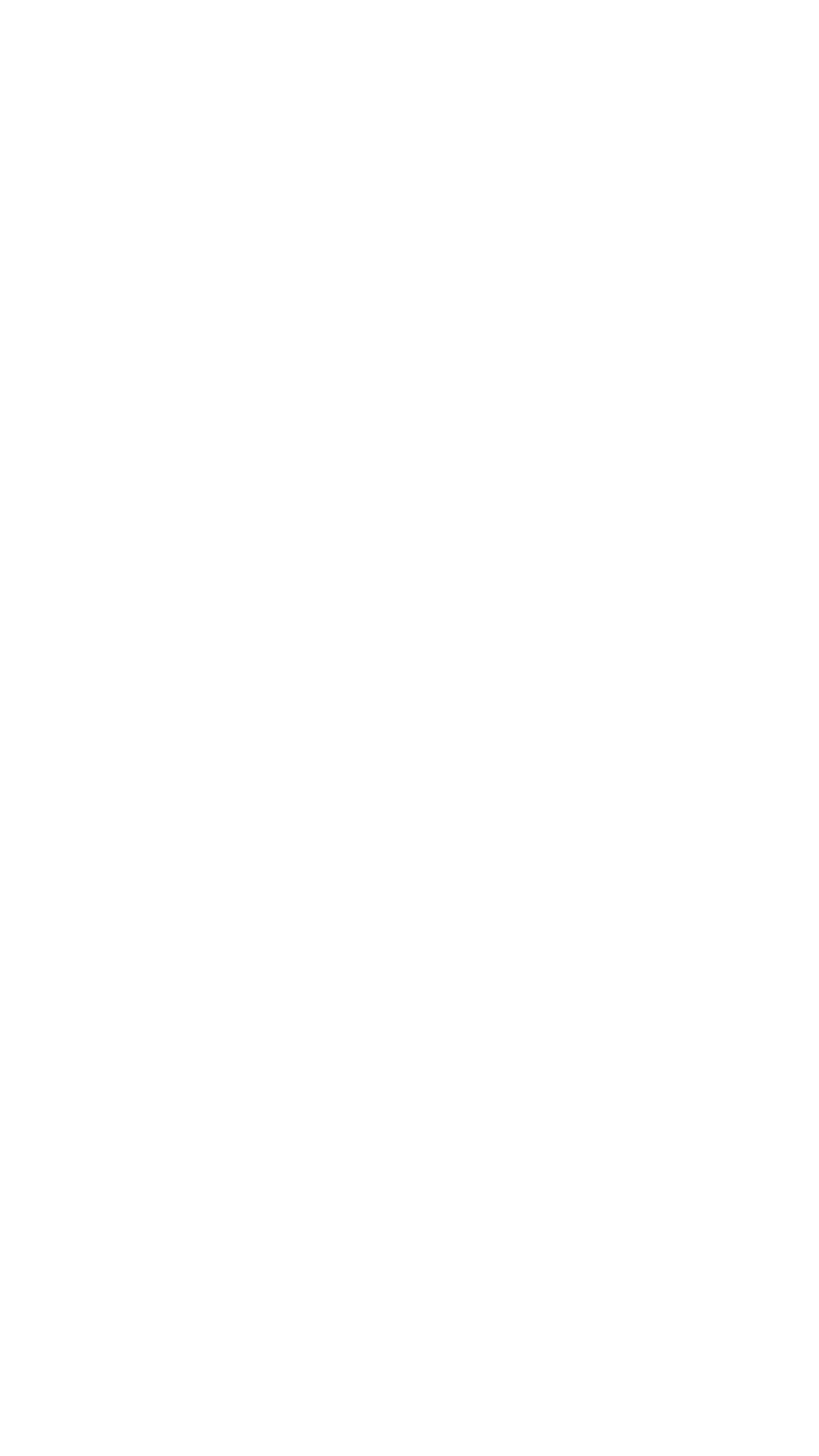
指でパテを均一の色になるまでこねていき、それからカラーパウダーをつけて更に均一の色になるまで、混ぜていきます。撮影用にサンプルのフロアーを使用しているので、こぼしたパウダーをパテにつけていますが、真似しないでくださいね。あと付属のビニール手袋だと非常に練りにくいので、指にフィットするゴム手袋などを使うといいです。ない方は付属の手袋で頑張ってください。
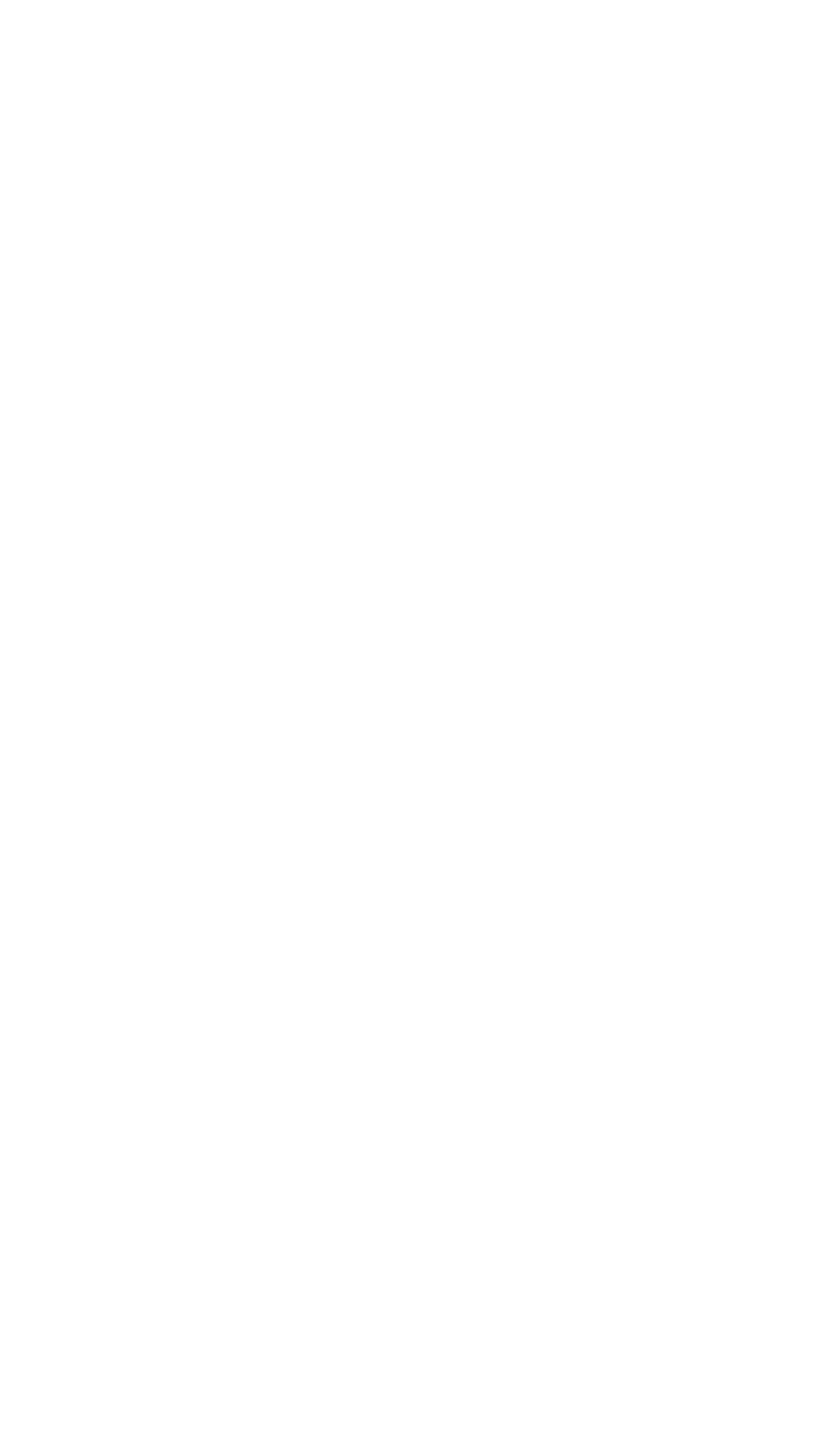
練ったパテを、付属のヘラで傷に埋め込んでいきます。傷の中心から外側に引くようにして盛っていきます。
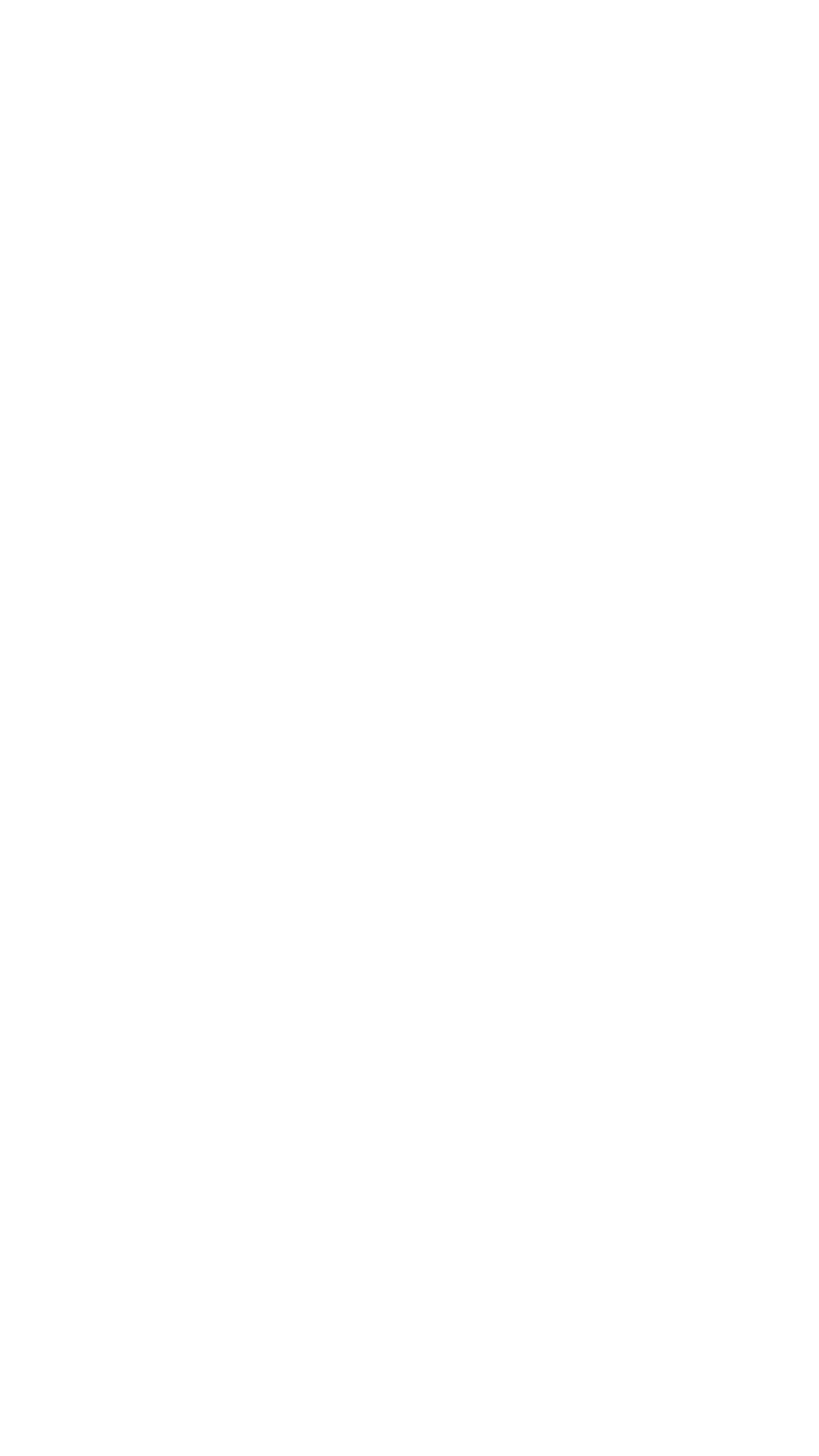
外側に引くように傷全部に埋めます。ポイントはパテで平らにしようとしないことで少し盛り上がっているくらいがベストです。
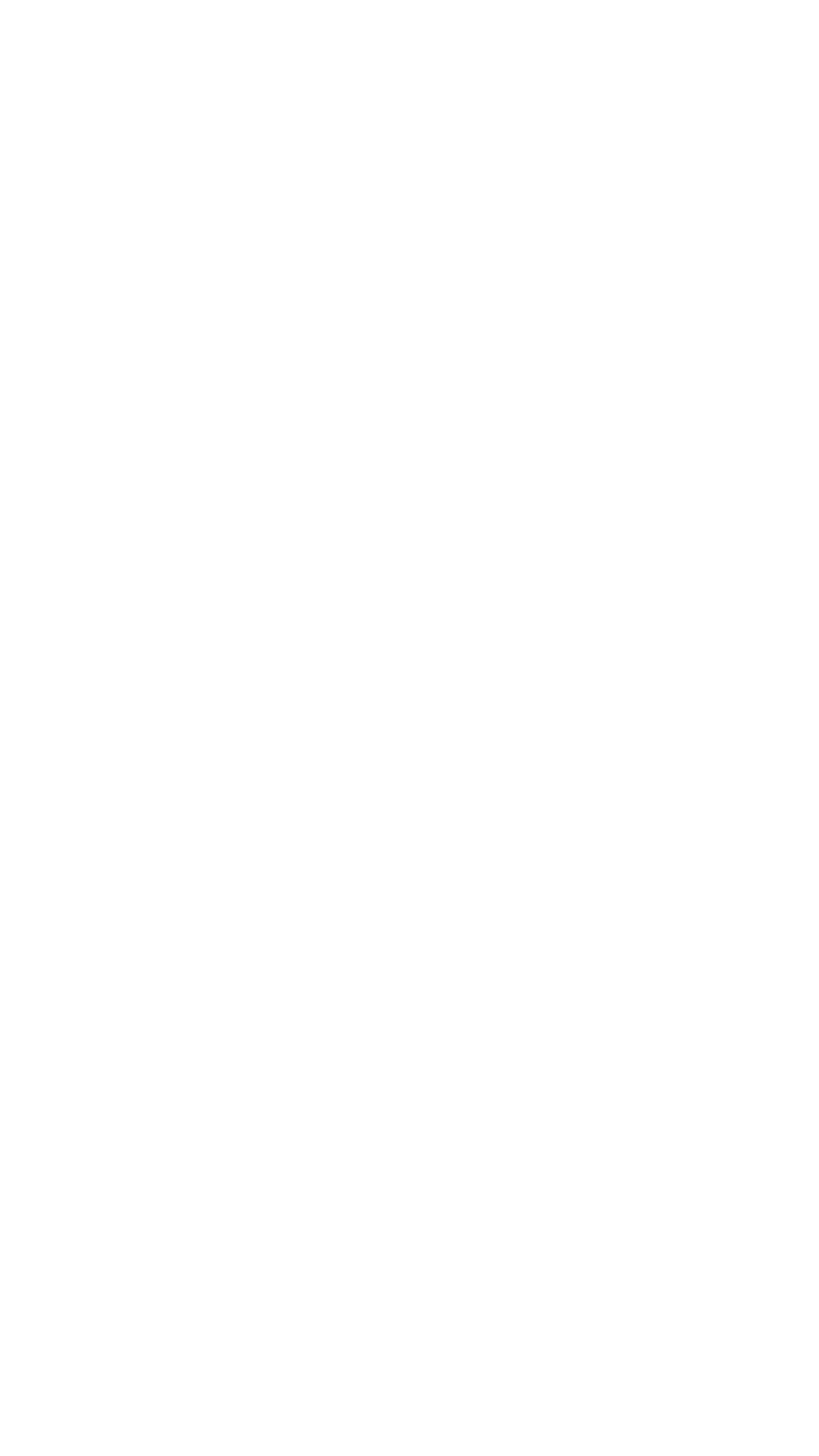
ヘラで盛ったパテを少し慣らしていきます。ここでせっかく埋めたパテを引っ張り取れることがあるので注意してください。ヘラにほんの少しだけ水をつけて、撫でてあげるとうまくいきやすいですがつけすぎてもダメですので、研磨が大変になりますが、自身のない方は慣らさずに硬化させてください。それにしてもこのヘラも非常に使いにくい。
これでパテ埋め作業は終わりです。パテを埋める時にヘラを使わずに指で、傷に押し付けて埋める方が簡単かもしれません。それと、埋め終わるまでにパテが固くなり始めてきたら、新しくパテを練った方がやりやすいです。色々チャレンジしてみてください。気温によりますが、30分から1時間で研磨できるくらいまでに硬化します。硬化するまで休憩するなどして待ちましょう。
次はパテの研磨作業です。
次はパテの研磨作業です。
4
埋めたパテの研磨作業
傷に埋めたパテを研磨していきます。240番のサンドペーパーを当て木か硬質ゴムなどに巻いて研磨。傷の周囲をなるべく削らないように心がけたいですが、少しは削れてしまいます。説明書の通りにパテを埋めるときにマスキングテープを貼っておいて、そのまま硬化させ、研磨した方が周囲は傷つきません。でも、マスキングテープの厚み分の段差は生じます。研磨してマスキングテープが削れてきたところで、マスキングを剥がして、段差を指で確認しながら、当て木なしで慎重に研磨します。
今回、私はマスキングなしでの研磨作業です。普段の作業ではマスキングはあまりしませんので。
今回、私はマスキングなしでの研磨作業です。普段の作業ではマスキングはあまりしませんので。
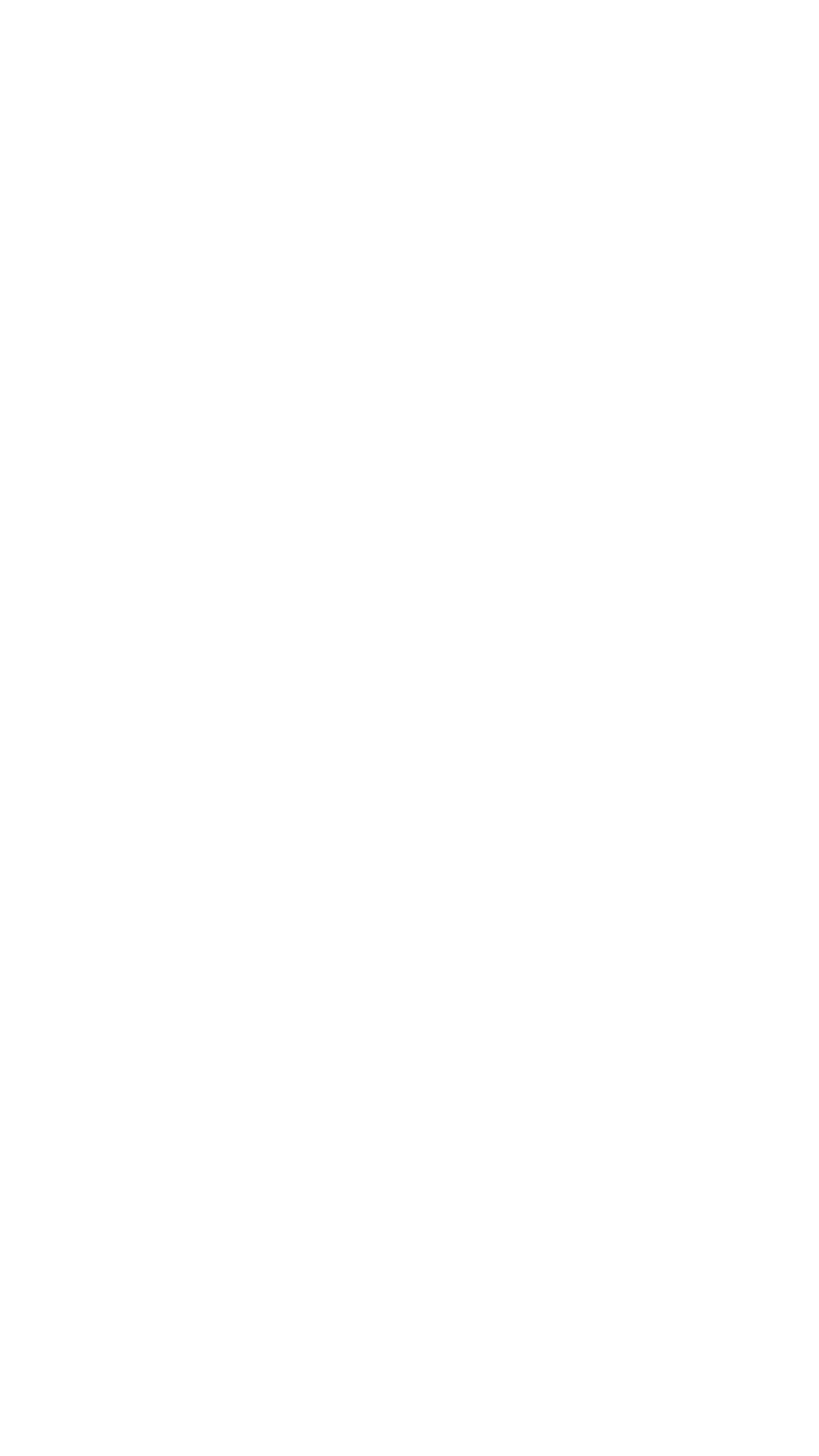
硬化したパテを平らになるまでサンドペーパーで削っていきます。
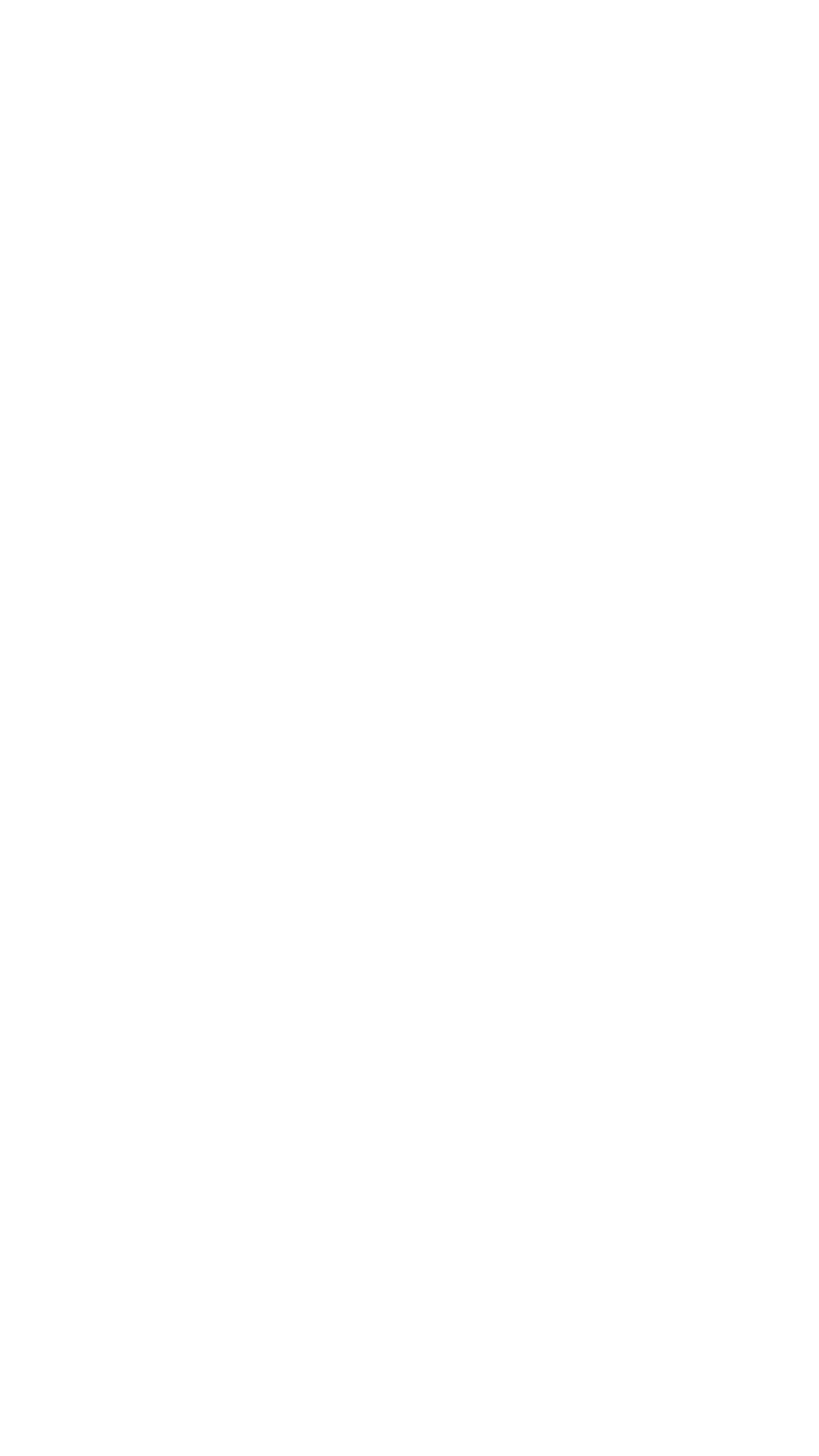
サンドペーパー240番を必要な分を切り、硬質ゴムブロック、当て木などを使い研磨していきます。
今回使用しているのは、KOVAXのトレブロックというものです。
今回使用しているのは、KOVAXのトレブロックというものです。
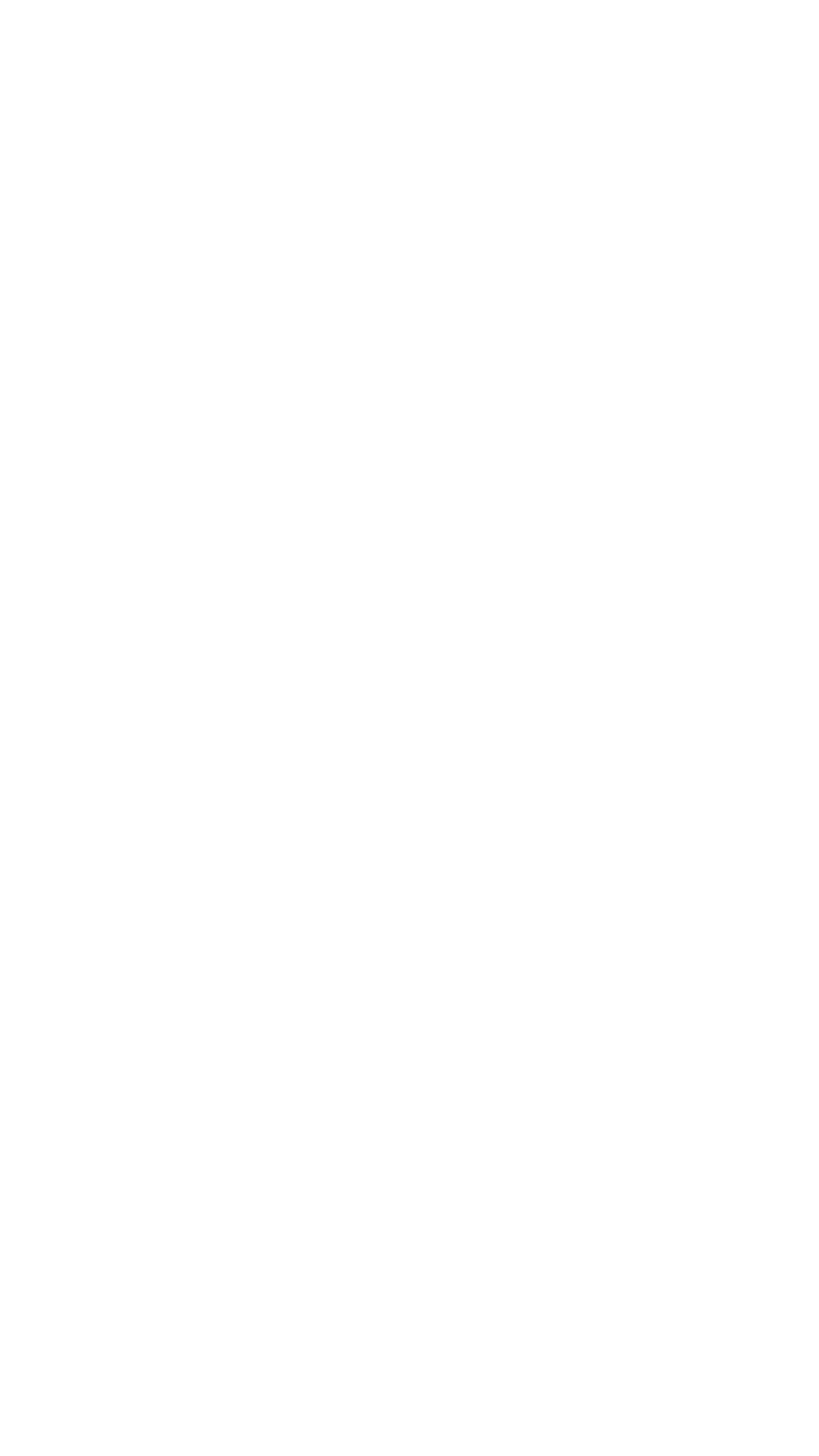
押し付けずに軽く削ります。
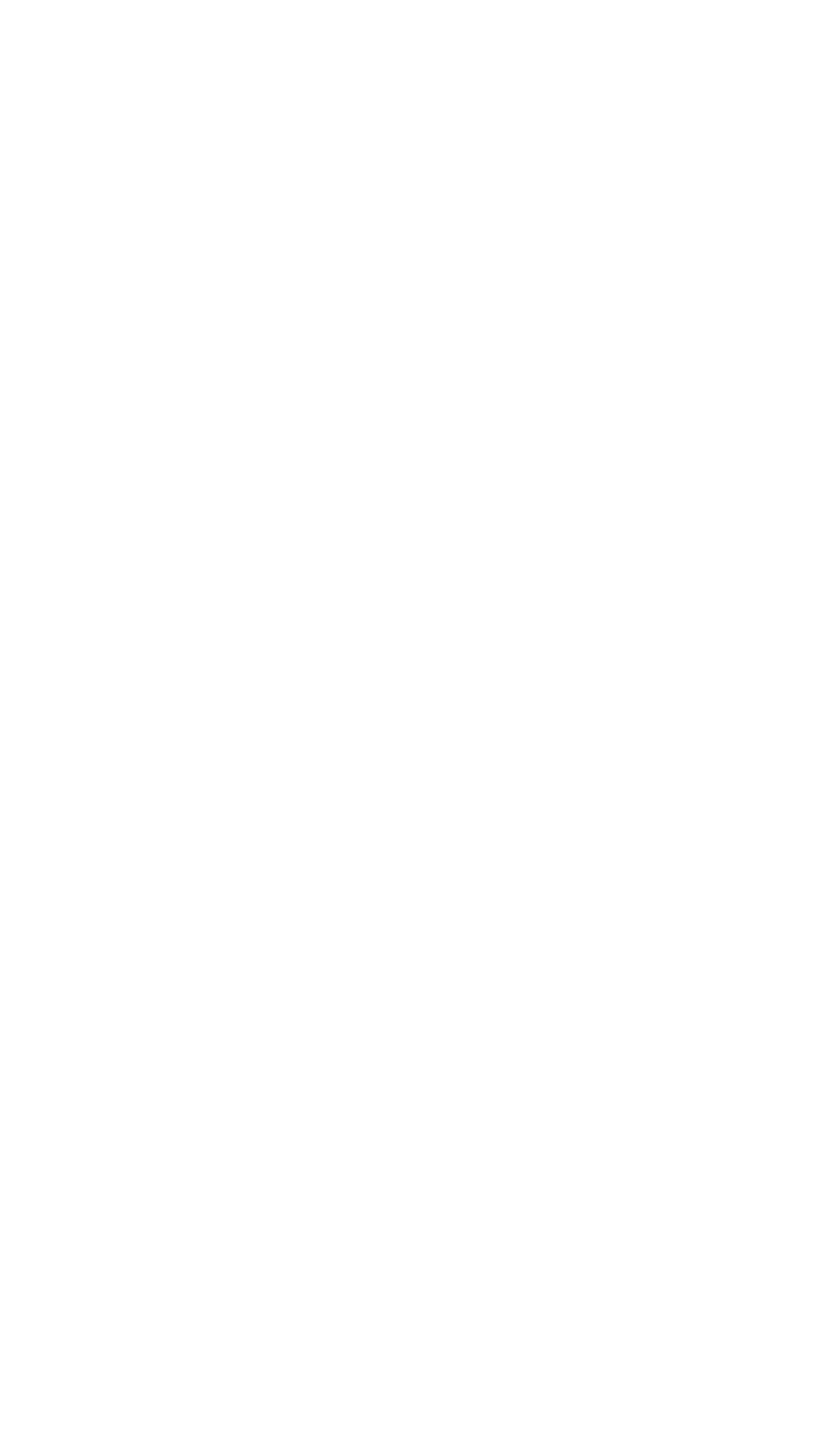
削れてきてるなと感じてきたら、途中で指で触りながら確認して削り作業をしていきます。
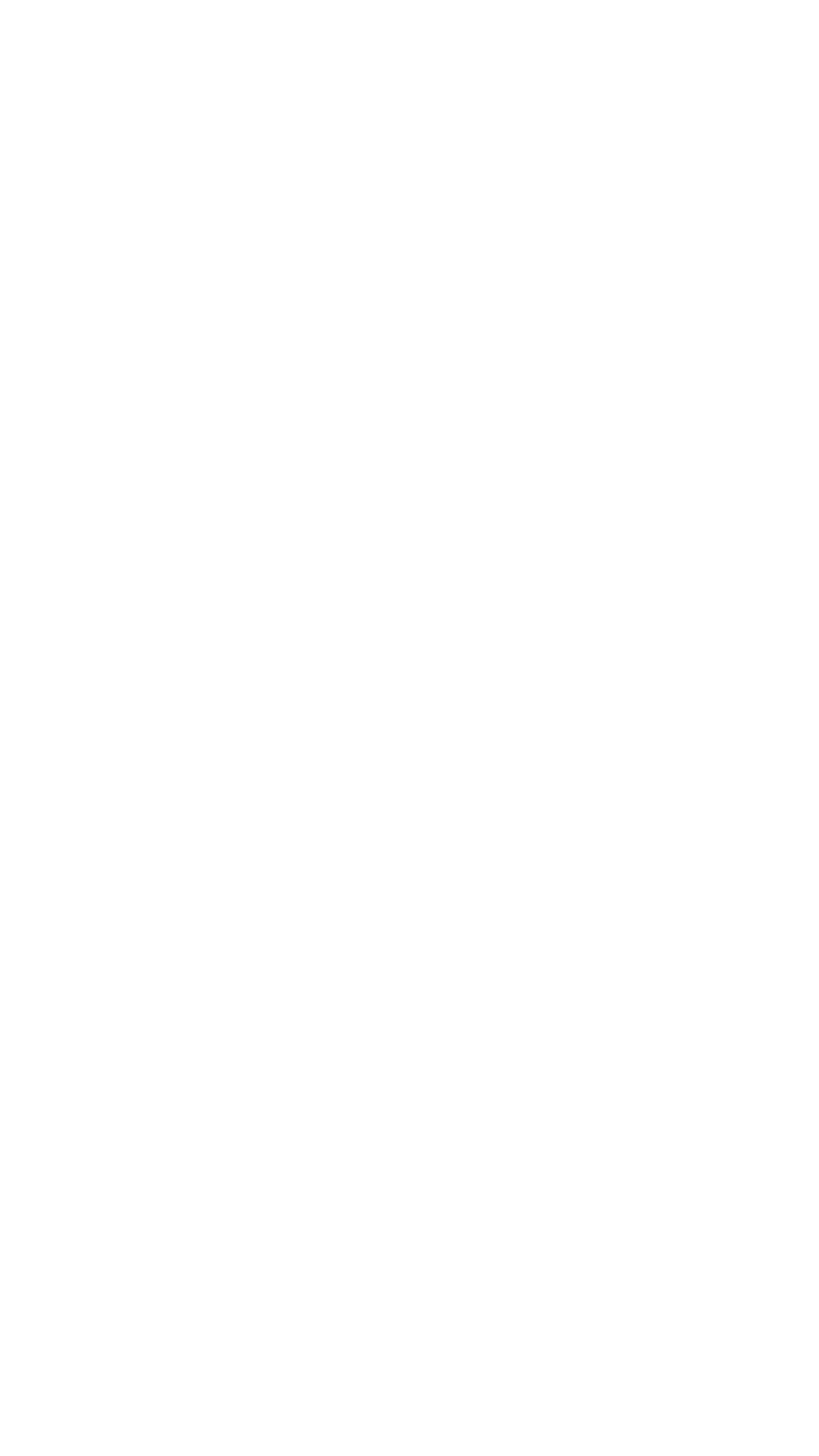
ウエスで粉などを拭き取るか、また掃除機で吸い取りながら作業。
ずっと当て木を使って研磨していけば、平になると思われがちですが
力の入れ方などで偏りますので、指で確認しながら高いところを当て木なしで削ります。
ずっと当て木を使って研磨していけば、平になると思われがちですが
力の入れ方などで偏りますので、指で確認しながら高いところを当て木なしで削ります。
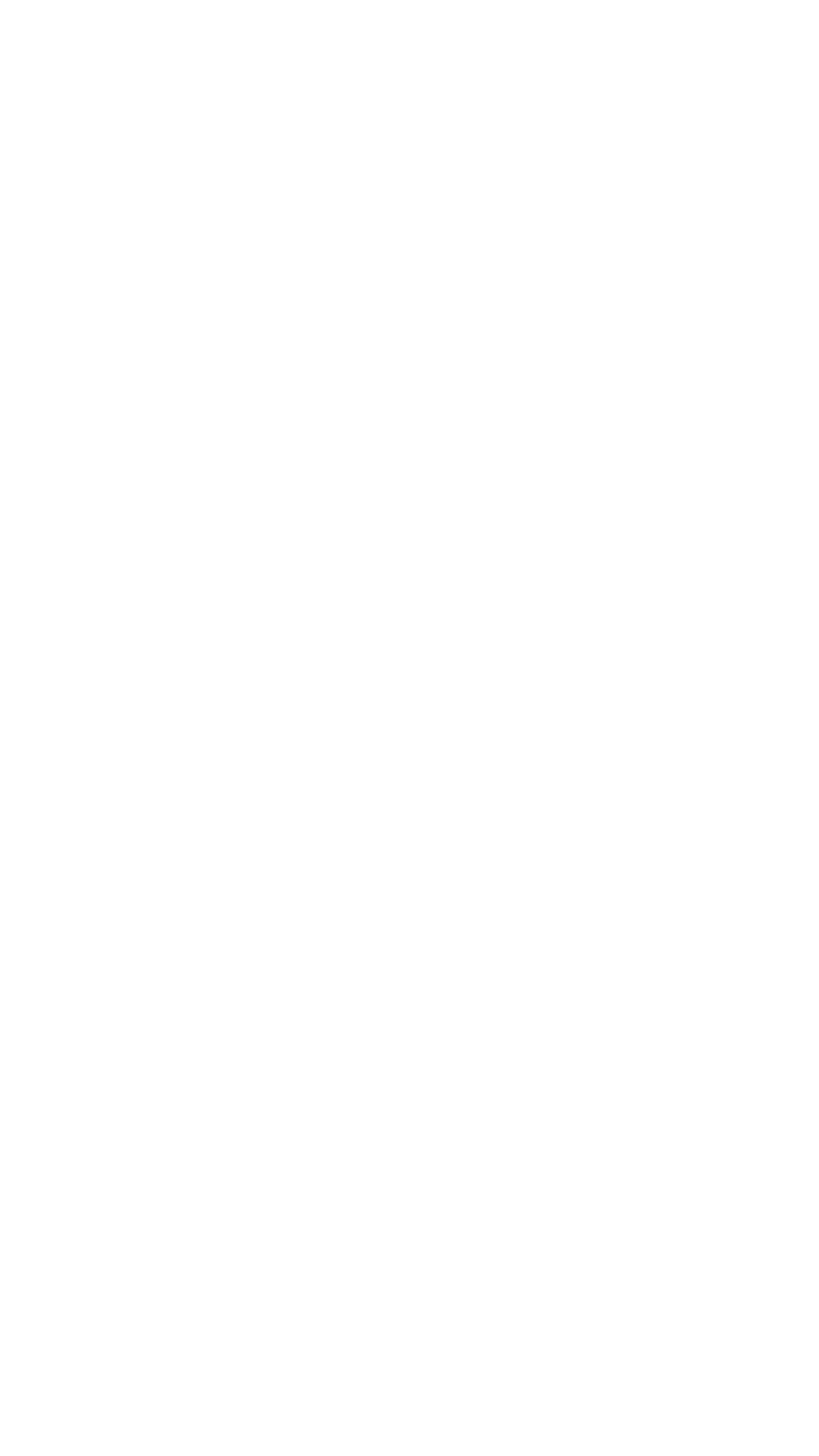
何度も指で確認しながら、削りすぎないようにして研磨終了です。
これで研磨作業の終了です。付属のサンドペーパーは意外と削れないので気合いで削るか、別途に空研ぎペーパー180番など使用するといいです。削っていって平らになっていったら、240番、320番などに変えていくといいです。削りすぎて凹ませないようにしてください。
5
着色作業
傷部分に周囲に近い色を塗っていき、木目など描いていきます。
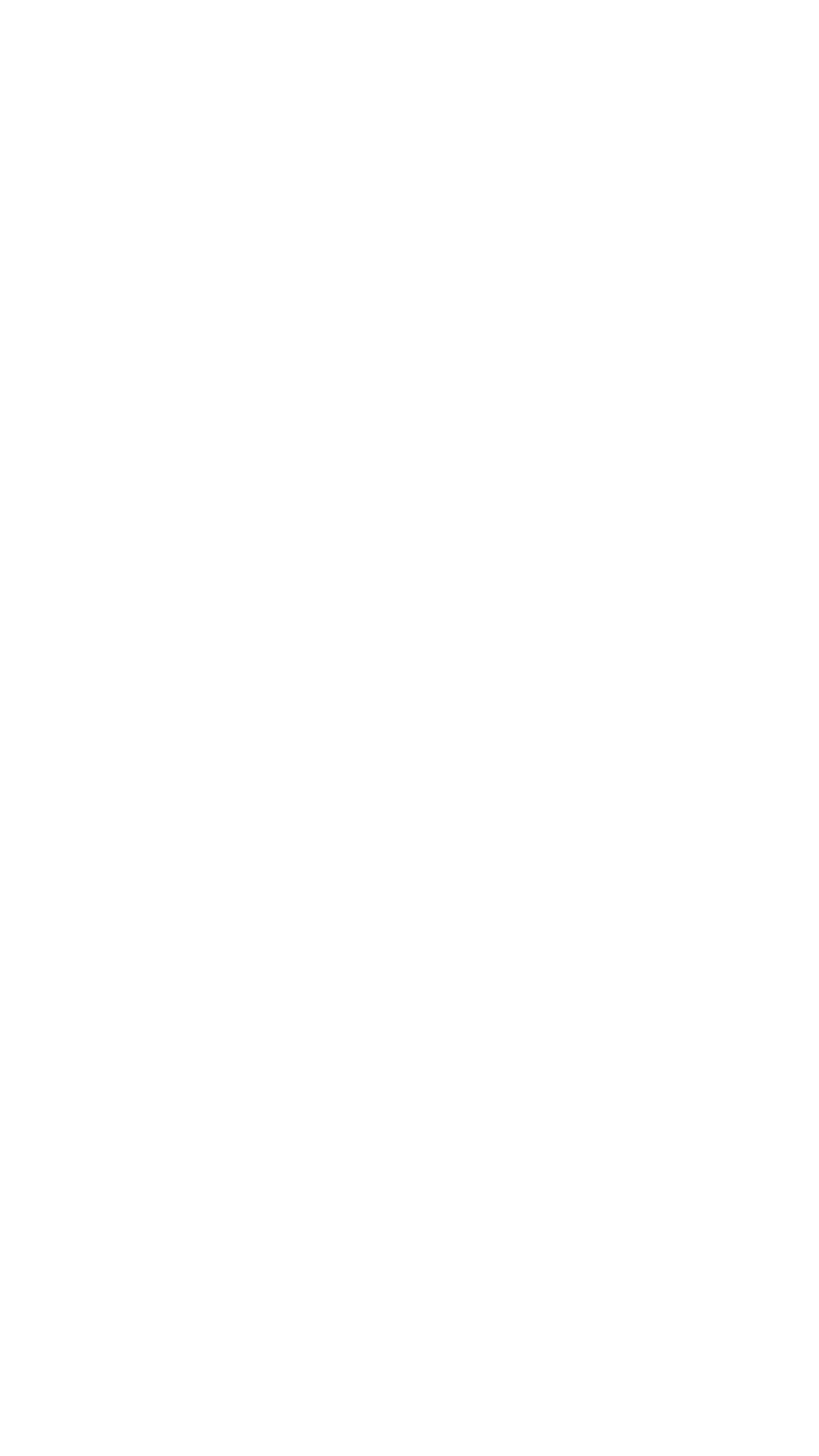
パパリペアセットのケースの蓋をパレット代わりに利用して、密着液を少量出していきます。
透明なケースの蓋は色を作るのにフロアーの色に合わせやすいのでとてもいいです。
透明なケースの蓋は色を作るのにフロアーの色に合わせやすいのでとてもいいです。
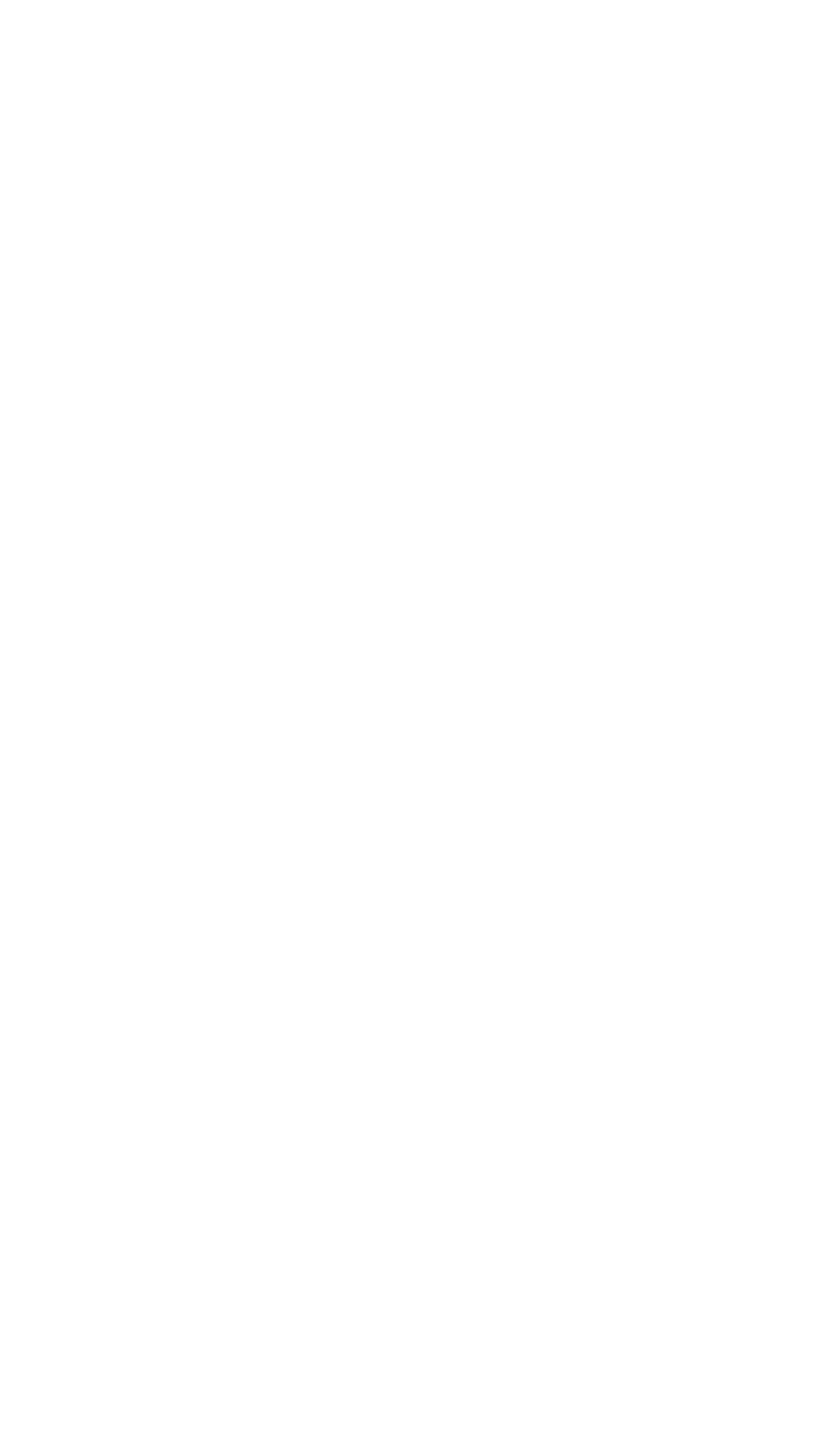
セットにあるカラーパウダーの中からフロアーに合いそうな色を選んで、少量ずつパレットに出していきます。
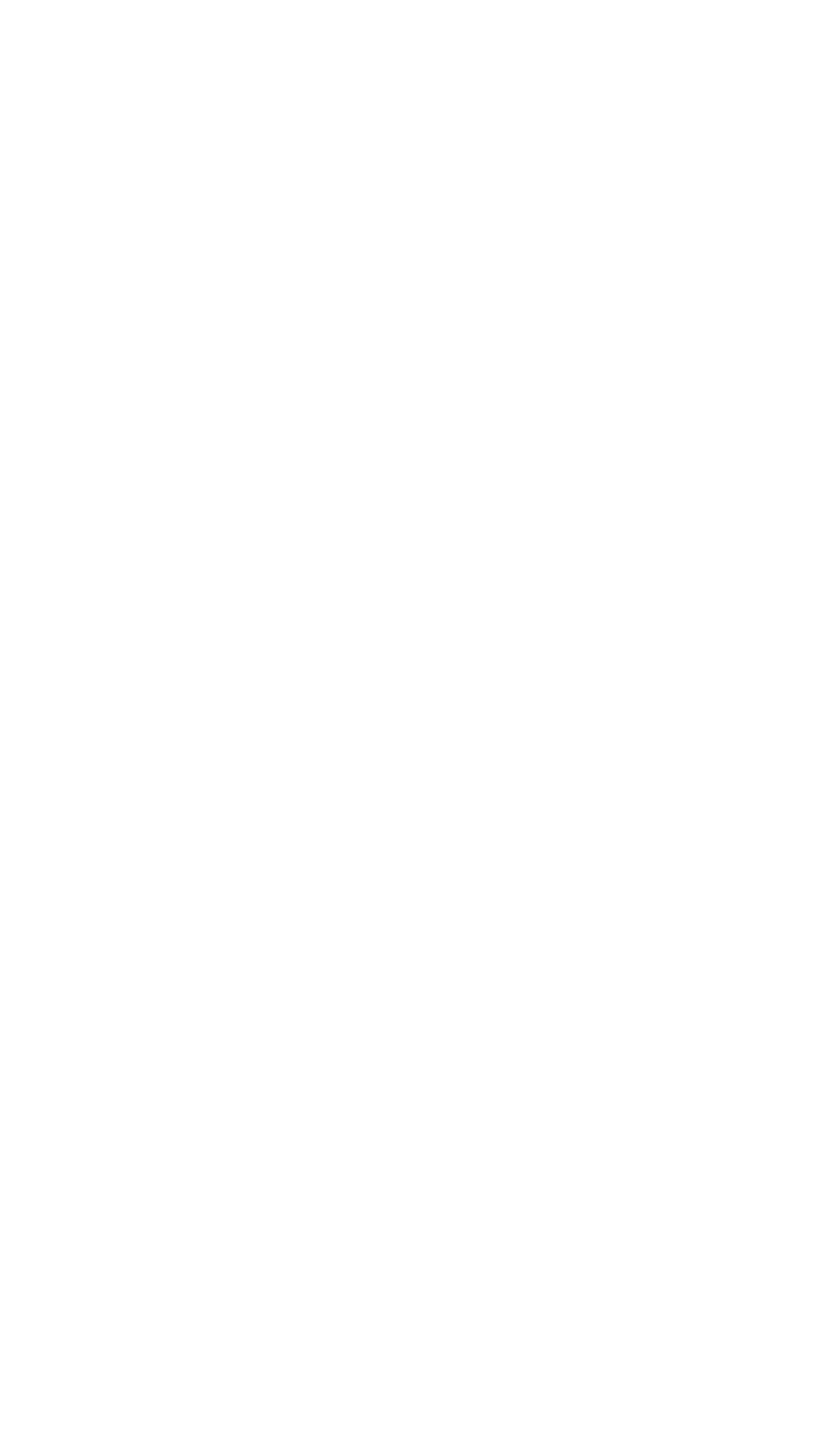
今回は黄色系、薄茶系、焦茶系、白のパウダーを選びました。
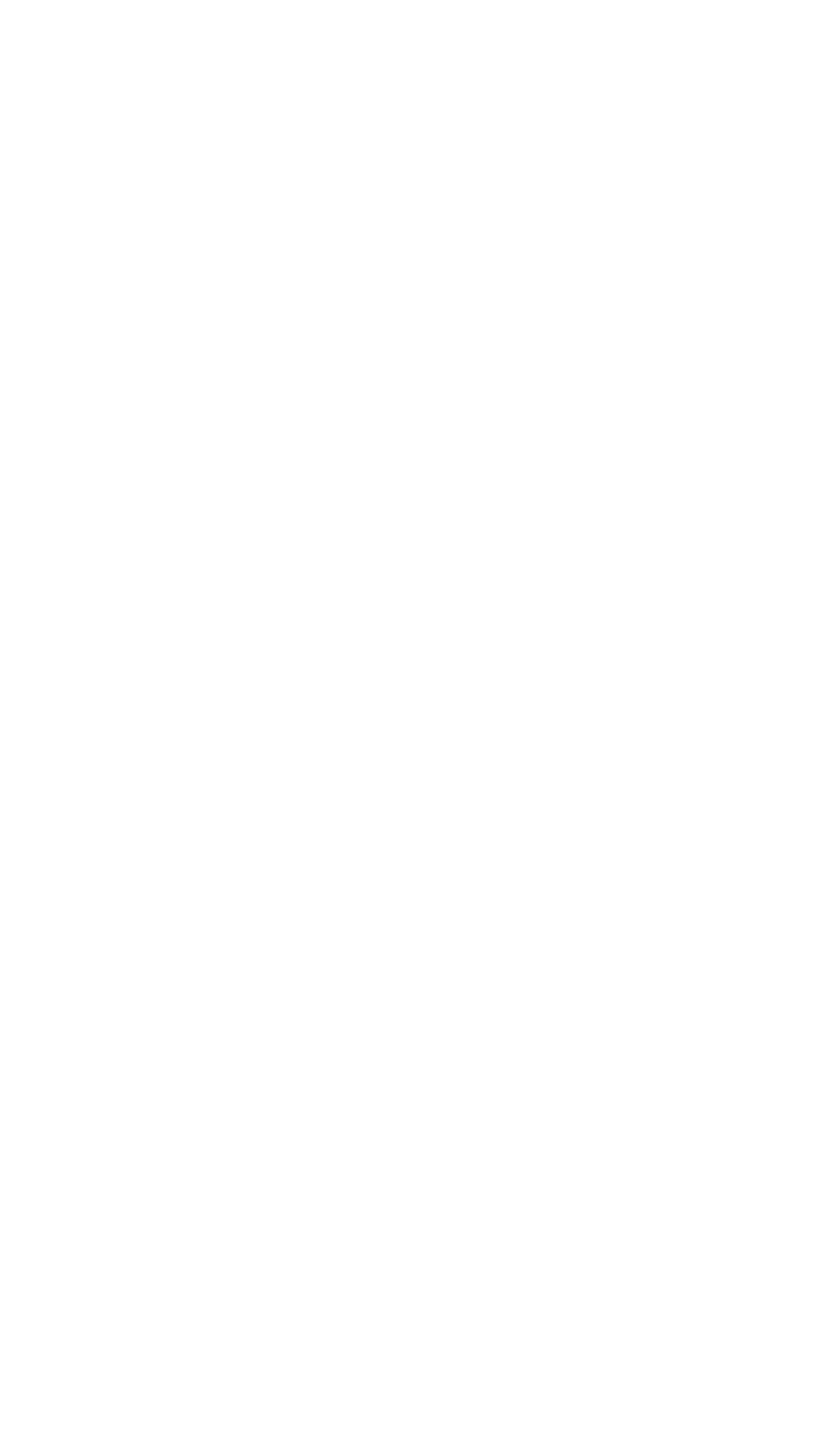
セットについてくる筆を使い、密着液にパウダーを少しずつ溶いていき色を調整していきます。
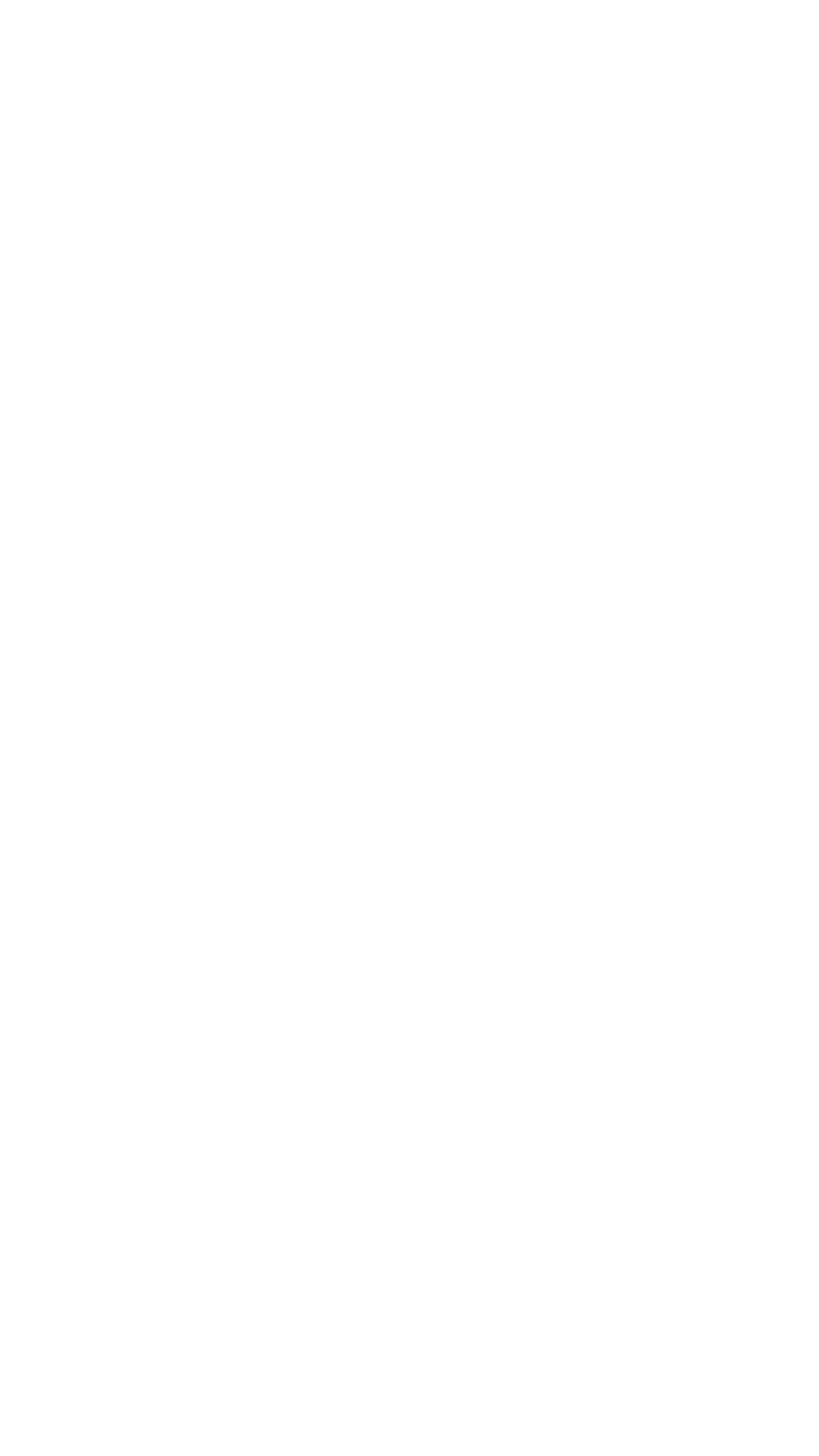
ある程度、近い色ができたらパテ部分に塗っていきます。
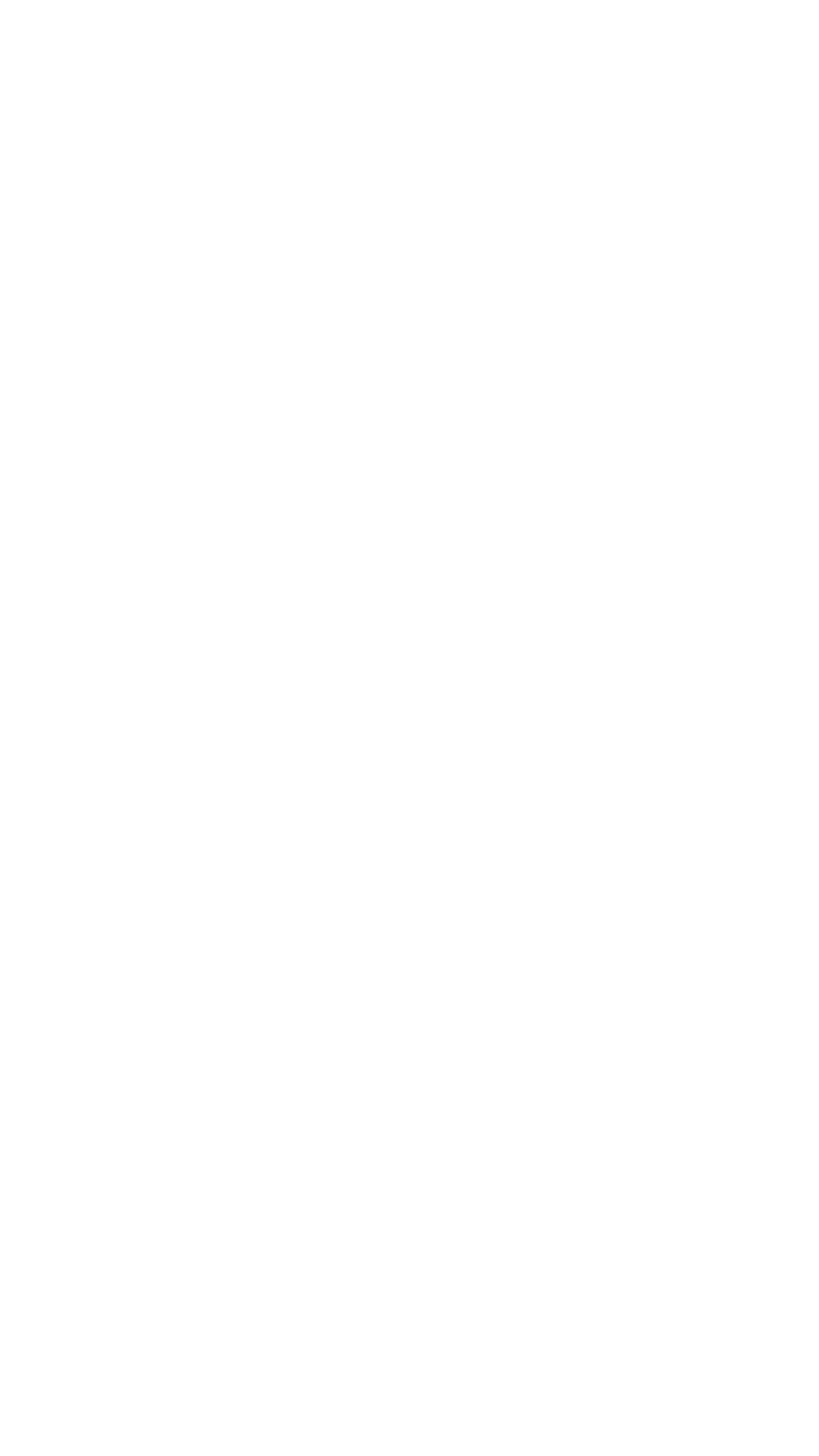
白い木目があるので、白で木目を描きます。
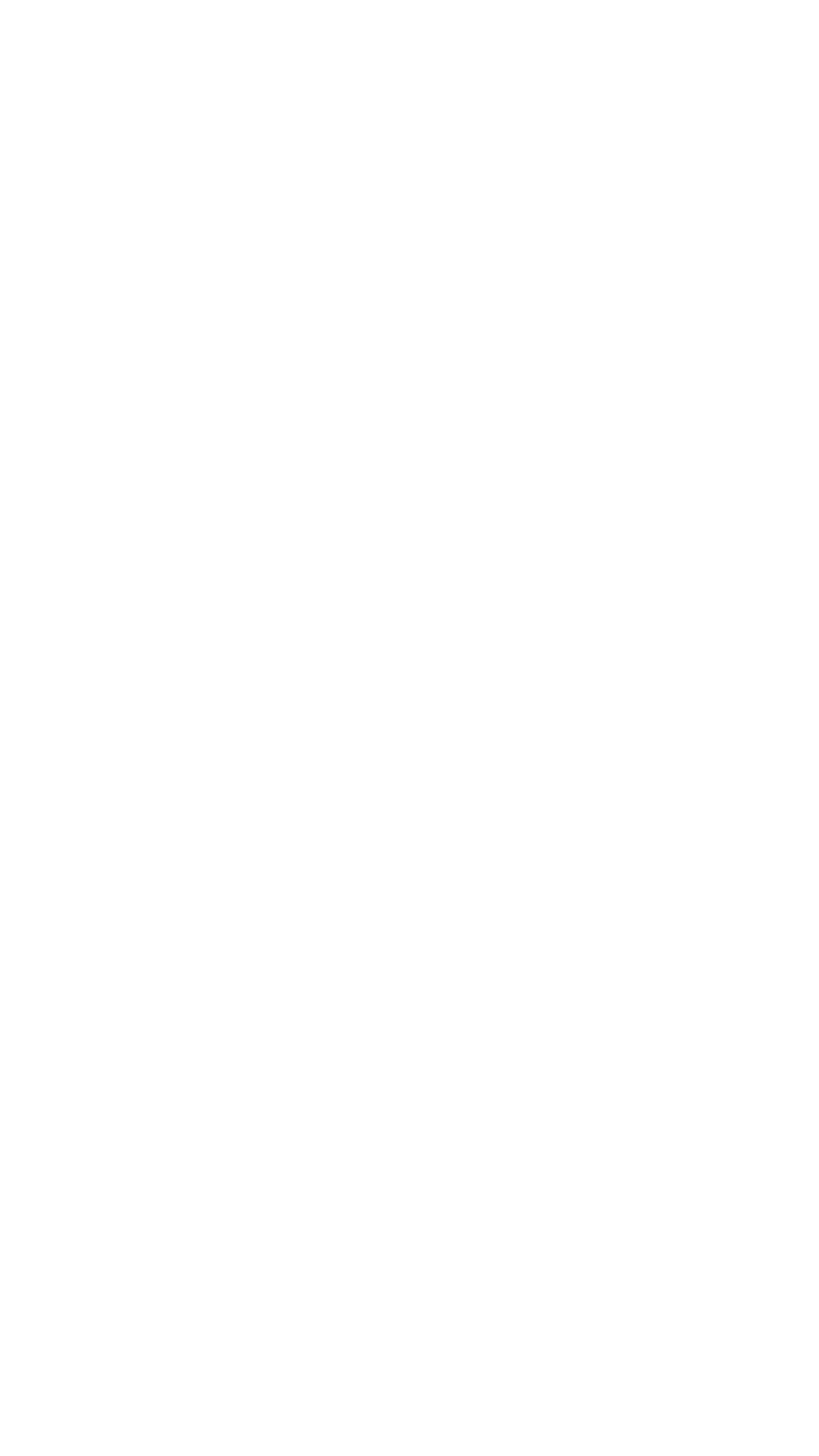
白の木目を足していき、様子を見て調整していきます。
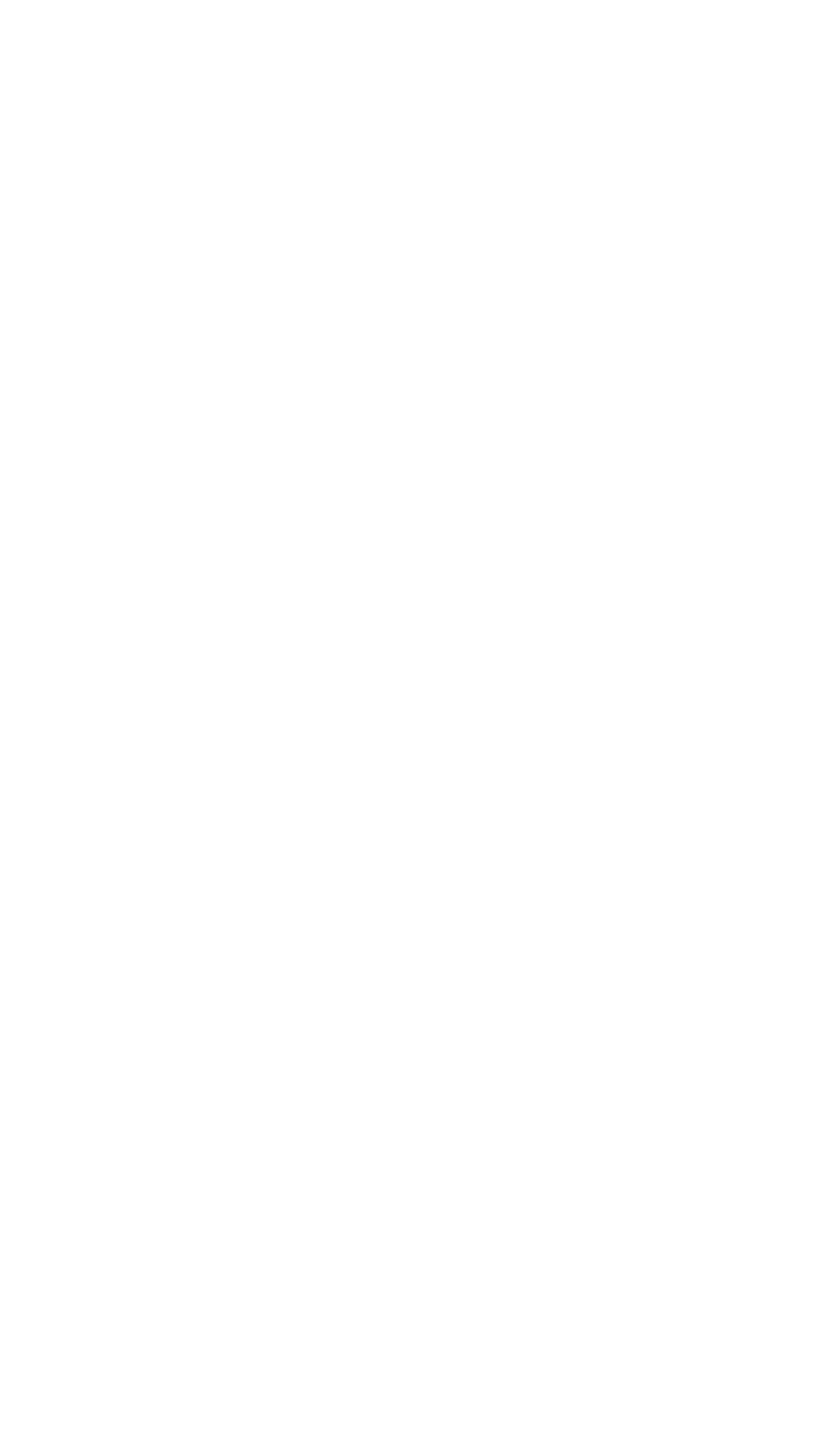
薄い茶色系を塗り重ねてぼかしいきます。
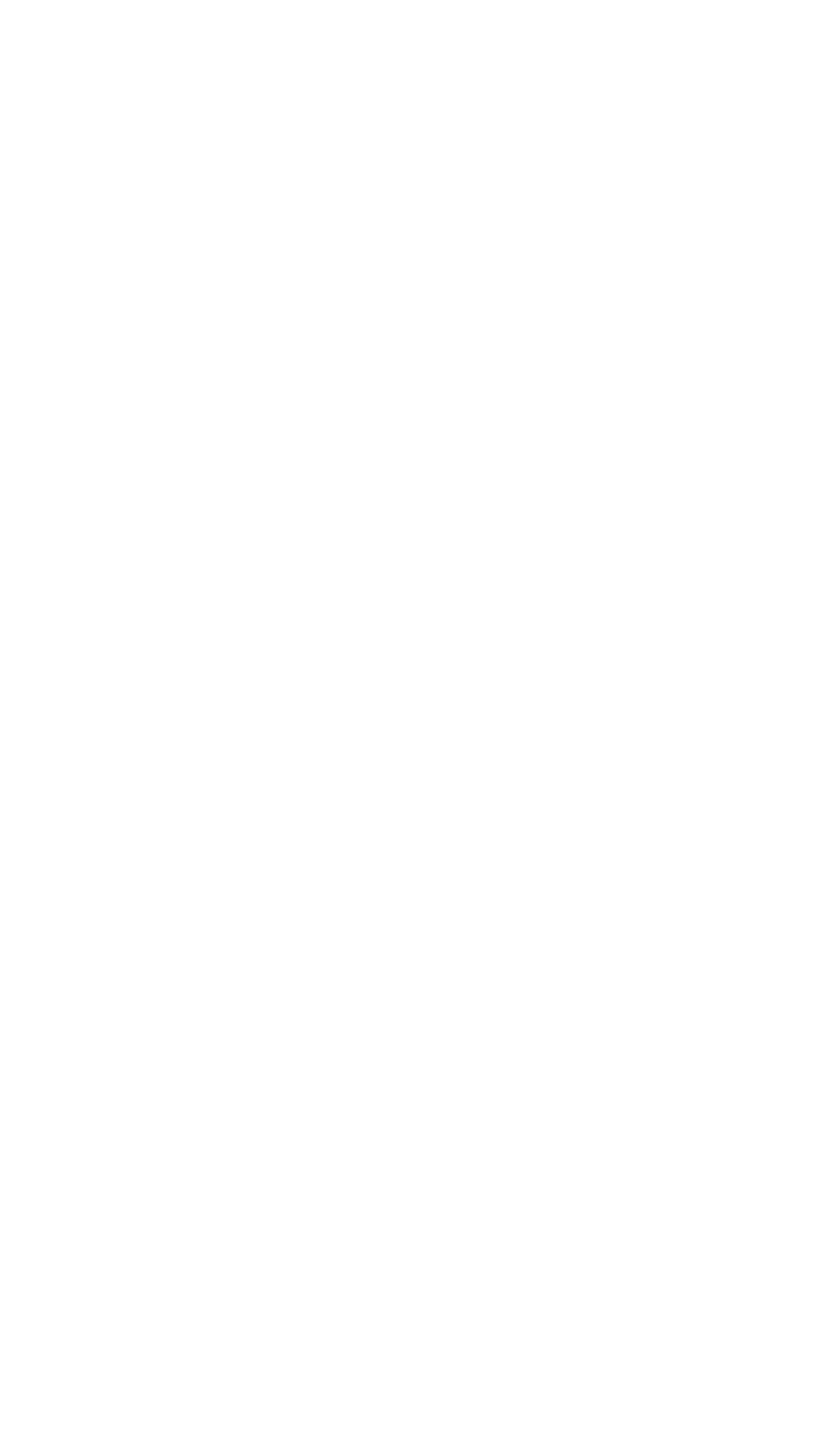
徐々に周囲に近づいてきました。後もう少し調整していきます。
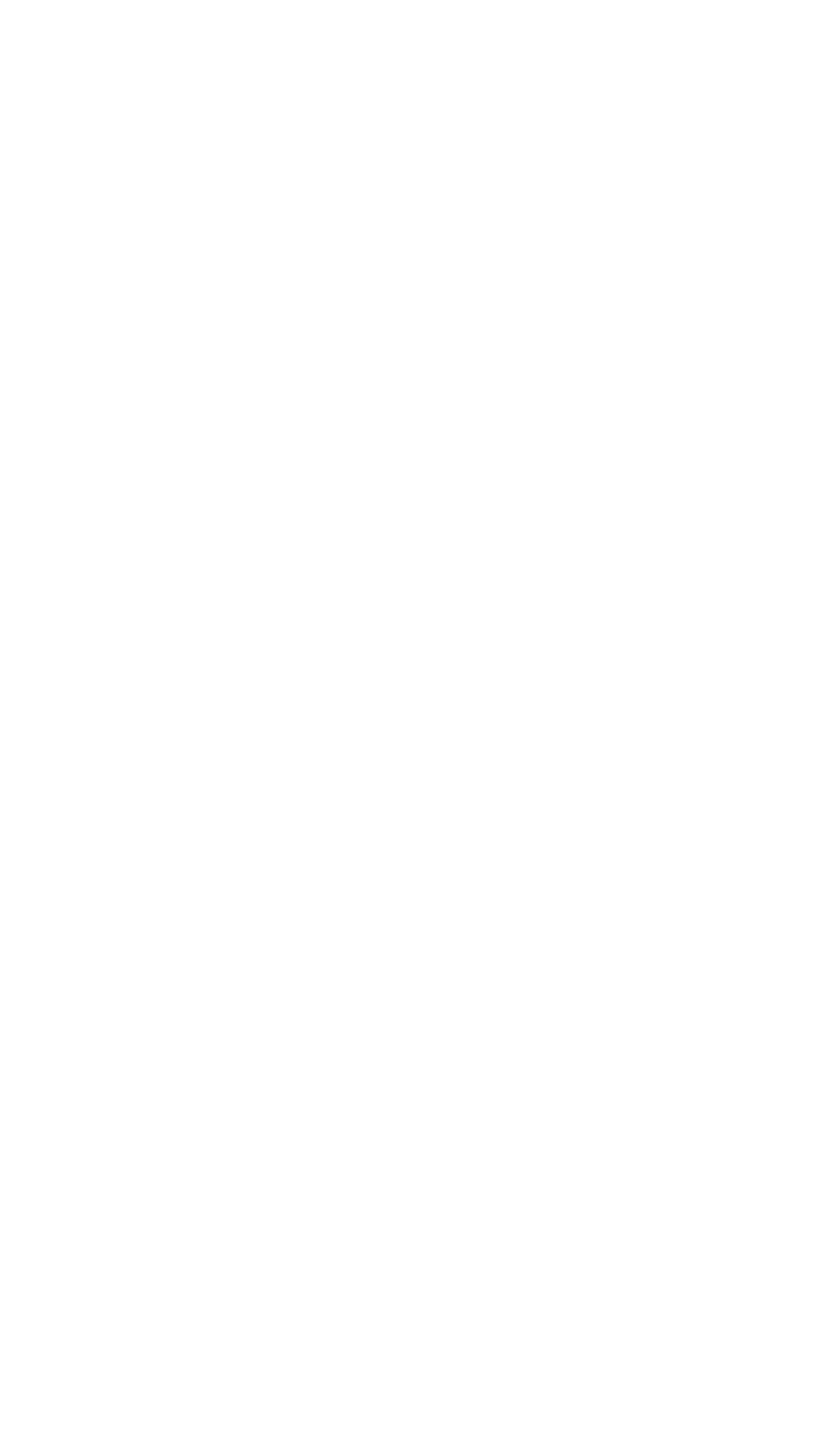
焦茶系の木目もあるので描いて調整。
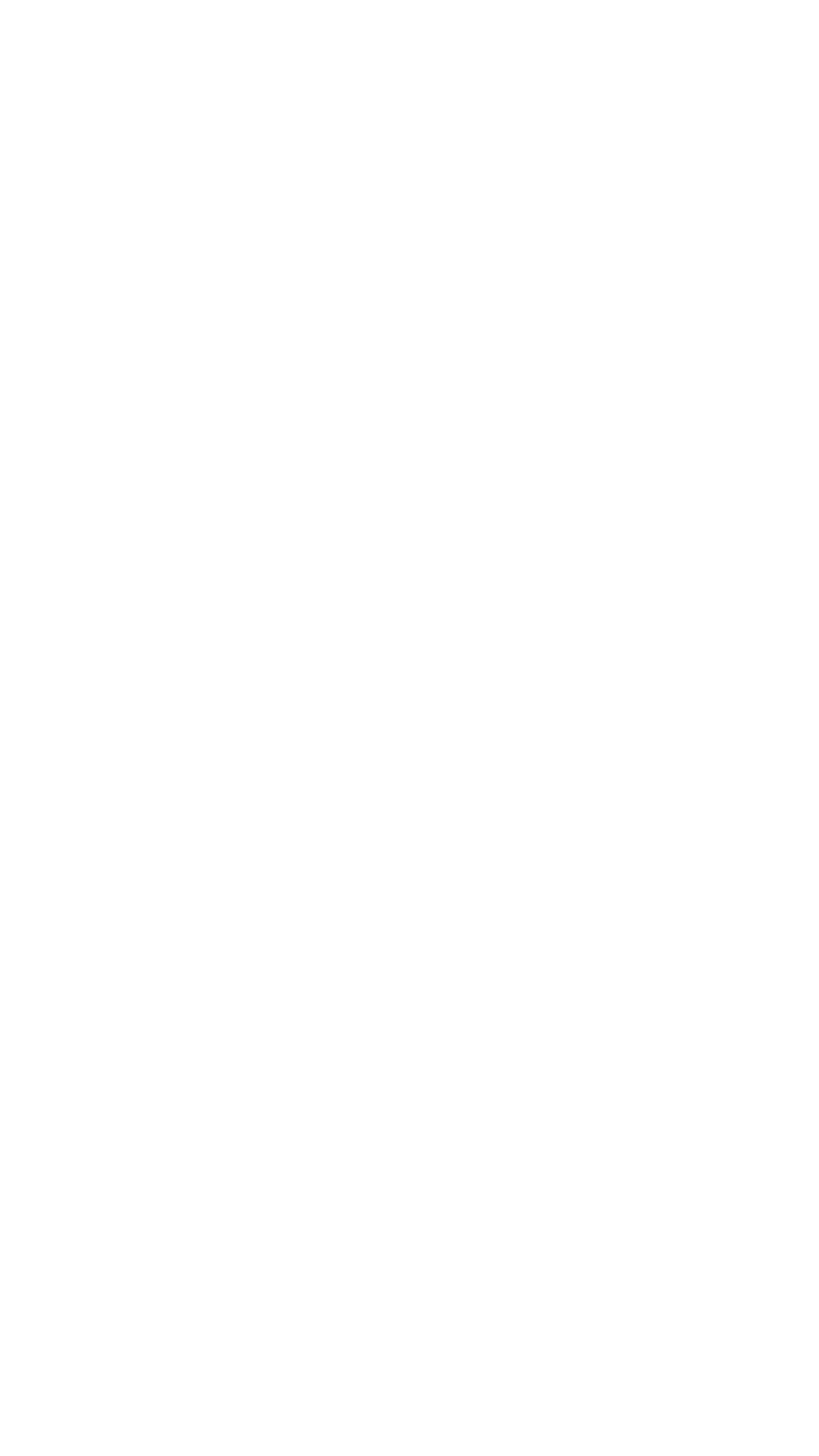
細かく調整しながら補修の完成です。
着色のポイント!としては、塗った後、乾くと少し色が変わるので一回の着色で色を合わせるのは難しいです。色を調整しながら塗り重ねていきましょう。あと、少し乾かないと前に塗った色が取れたりしますのでじっくりと着色してください。
補修作業の様子は動画にしてありますので、参考にしていただければと思います。
補修作業の様子は動画にしてありますので、参考にしていただければと思います。
パパリペアセットでDIYフロアー補修動画